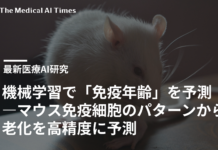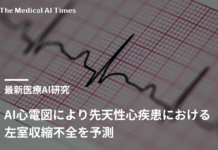注意欠陥・多動性障害(ADHD)の診断は、主要な症状の有無に関する主観的評価が中心となるため、診断の遅れや誤りが生じるといった課題があった。より効率的で信頼性の高い客観評価のため、米イェール大学のチームは、脳MRIから機械学習手法によってADHDを診断する研究に取り組む。
北米放射線学会(RSNA)の年次総会で発表される同研究では、9-10歳の小児が参加した米国最大級の思春期脳認知発達研究(ABCD study)のデータを活用している。ADHD児1,830人と、非ADHD児6,067人のMRIデータを用い、ADHD診断に有用なバイオマーカーを探索した。その結果、ADHD児においては、脳皮質の薄化、前頭葉における白質微細構造の著明な変化など、多様な構造的特徴が抽出されたとする。これらの画像特徴からADHD児の予測が可能となり、モデル性能はAUC 0.6085を示していた。
イェール大学医学部のHuang Lin氏は「多くの先行研究において、ADHD児の脳特定領域の変化を同定してきたが、我々の研究結果では、脳のほぼ全ての領域で変化を認めている。このことは、ADHDが純粋な行動障害ではなく、脳内に神経構造的・機能的な兆候を有する神経疾患であることを裏付けている」と語っている。
関連記事: