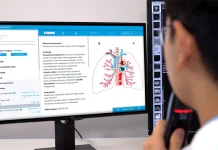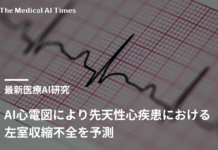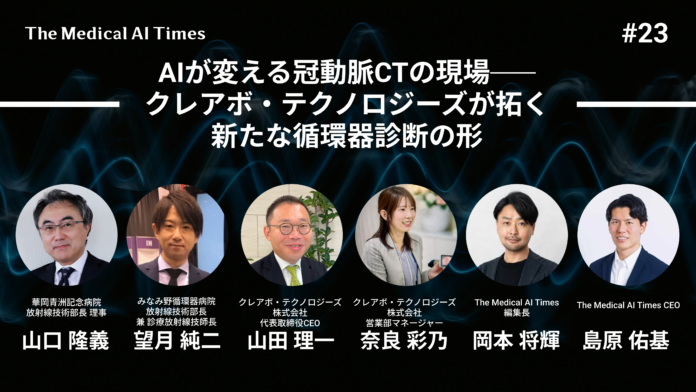この記事は、The Medical AI Times Podcast第23回(クレアボ・テクノロジーズ株式会社協賛回)をもとに編集・構成したものです。
ポッドキャスト音源とあわせて、テキストでも情報をキャッチアップできるようにお届けします。
【番組概要】
■配信日時:2025年10月29日
■出演者:
クレアボ・テクノロジーズ株式会社
代表取締役CEO 山田理一
営業部マネージャー 奈良彩乃
華岡青洲記念病院
放射線技術部長 理事 山口隆義
みなみ野循環器病院
放射線技術部長 兼 診療放射線技師長 望月 純二
The Medical AI Times:岡本将輝 / 島原佑基
■配信ページ:
YouTube:https://youtu.be/ExkhJQcqWT8
※本記事は医療従事者向けです。医療機器(および一部未承認機器)に関する言及を含みます。
企画:The Medical AI Times/協賛:クレアボ・テクノロジーズ株式会社
企画の趣旨と本日のゲスト
島原:The Medical AI Times Podcastへようこそ。The Medical AI Timesの島原です。
この番組では、医療AIに関する最先端の情報をお届けしています。
本日は、編集長の岡本さん、そして4名のゲストの皆さまをお招きして、お話を伺いました。
臨床の現場で実際に活用されている、現場の“解像度の高い”リアルなお話を深掘りしていく中で、どうしても製品に関する情報にも触れる必要が出てきます。
そのため、メーカーの方々や臨床の先生方、双方の視点を交えながら、教育的な側面やPRの観点も含めて、企業協賛という形での実施ができないか——そんな話を以前から続けてまいりました。
そして本日、その第一回が実現いたしました。
つい先ほど収録が終わったところですが、岡本さん、いかがでしたでしょうか?
岡本:非常に面白かったですし、私自身あまり詳しくなかった冠動脈CTという分野で、最先端で取り組んでおられる先生方がどのような思いで臨床に向き合っているのかが伝わってきました。
また、先端技術が果たせる役割についてもお話しいただけたので、今後の展開が楽しみだと強く感じられる内容になっていたと思います。
島原:本日は、循環器領域におけるCT技術の第一線でご活躍の先生お二方、そしてクレアボ・テクノロジーズからお二人のゲストをお迎えしております。どうぞお楽しみください!
島原:それではゲストの皆様から自己紹介をお願いいたします。
山口:華岡青洲記念病院の山口と申します。
今回は当院で「CareverseTM CoronaryDoc」というAIソフトウェアを導入したことから、このような機会をいただけたのではないかと感じております。
今回のテーマは冠動脈CT、心臓CTということで、私自身は25年前に4列というCTを用いて心臓CTを始めました。皆様ご承知のように、心臓CT、冠動脈CTの分野は年々レベルが向上しており、現在は一般的な検査となり今後も適応拡大が見込まれます。私が所属しているのは循環器の専門病院であり、冠動脈CTを中心に診療を行っています。320列CTを三台導入しており、日々検査を行っている状況です。本日はいろいろとお話しできたらと思っております。
望月:みなみ野循環器病院の望月です。私は心臓CTを専門としてから15年ほどとなりますが、山口先生が考案された手技や検査方法を臨床に活かしつつ、現在は主に心臓CTの画像解析の研究や企業との研究開発に携わっております。未だに心疾患はがんに続く第2位の死因であり、心臓で亡くなる方を検査の立場から少しでも減らしたいという信念を持って現在活動しております。本日はよろしくお願いいたします。
山田:クレアボ・テクノロジーズの代表を務めております山田と申します。当社は臨床現場の課題解決を目指し、医療AI製品を世界中から発掘して医療機器として開発・マーケティングする会社で今期は五期目となります。本日は皆様にクレアボという会社の名前だけでも覚えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
奈良:クレアボ・テクノロジーズ 営業部の奈良と申します。私は現在は冠動脈CTの解析AIのほか、医療AIソフトの販売に携わっております。今後もこのような医療AIを国内で広めて、医療の課題解決にお役に立てればと考えております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
現場の“いま”:即日読影が求められるワークフロー
島原:早速、内容について深堀りしていきたいと思います。このポッドキャストをお聞きになられているリスナーの中には冠動脈CTについてあまり詳しくない方もいらっしゃると思いますので、まずは、山口先生が日々取り組んでいらっしゃる冠動脈CTや臨床現場での現在の役割についてお伺いしたいと思います。
山口:当院は循環器の専門病院で、カテーテル治療だけでなく手術等にも対応できる病院となっております。外来の患者様はそういった専門的な診療を求めて来られる方がほとんどです。当院で行っているCT検査の多くは冠動脈に関与する検査で、検査全体の90%以上が外来で行う検査となります。そのような背景から検査結果は即日お伝えすることにしております。撮影から画像解析に至るまで、スピードを求められている状況です。
島原:ありがとうございます。遠隔読影に出さず、即日対応されているというのは、多くの医療機関でも一般的なのでしょうか?それとも、やはり珍しいケースなのでしょうか。
山口:難しいのではないかと思います。当院には放射線科医が2名在籍し、心臓に限らず体幹部の読影にも対応しています。紹介で来られる患者さんの紹介元の先生方からもご好評をいただいていると考えております。
島原:即日で検査結果を返されている点について、岡本さんご意見ございますでしょうか。
岡本:私たちが本職で開発している製品も、まさに「読影」に関わる部分が非常に重要な要素になっていまして、先生たちの読影負担は本当に大変だといつも感じております。
モダリティによって画像種ごとにも違いがありますし、それぞれに対応していくとなると、即日での対応などには並々ならぬご努力があるのだと思います。
もちろん、放射線技師の皆さまのご尽力もあってこそ成り立っている部分も大きいですし、大変な取り組みであるだろうと想像しております。
島原:ありがとうございます。世界的に見ても研究面、技術面で日本の技師は高く評価されていると思います。その体制を可能にするために日々どのような取り組みをされているのか、お聞かせいただければ幸いです。
山口:今現在、即日に結果を出すには、やはりマンパワーが重要になります。当院では月に約600件の冠動脈CTを実施しており、多い日には1日に約40件行っている状況です。撮影が終わってから30分から1時間弱の間に解析をすべて済ませて、読影を行いますが、この流れを作るには画像解析を専門とする配置が重要になってきます。ここ数年で非常に多くの技師を採用して対応している状況です。
島原:ありがとうございます。望月先生にもお話を伺いたいのですが、望月先生も放射線技術部長として支え、地域医療にも様々な活動をされていると伺っています。AIの活用や普段の工夫などについてお聞かせいただければと思います。
望月:当院は山口先生のところと比べると規模がやや小さく、CTも一台となります。しかしながら実施している内容はほぼ同様で、当院では冠動脈に限らず心臓全体の評価が求められています。
その理由としては、血行再建のPCIやアブレーションが毎日多数入っている一方で、カテーテル装置が一台しかないため、検査のみを目的としたカテーテル検査を可能な限り減らすことを目標としています。
心臓CTは1日に20から30件ほど撮影しておりまして、翌日には30分以内に結果を医師に返す体制を取っております。こうした体制を支えているのはワークステーションの精度向上であり、その中でAIは日常的に活用されています。現場では、どの工程でAIが用いられているかを意識しない場面もあるほどで、今後はより確実で精度良く進んでいくことを期待しています。
島原:まさにワークステーションにおけるビジュアライゼーションの分野では、AIは古くから使用されており、今では診断を支援するようなAIも存在するかと思います。AIを自然に使われているというのは放射線科の一つの特徴でもあると感じました。AI領域で長く活動もされている岡本さんからもコメントをいただければと思います。
岡本:私自身は心臓CTや冠動脈CTについては専門分野ではないのですが、この領域においてAIは、すでになくてはならない存在となっているのでしょうか。
他の放射線画像におけるAIの位置づけからすると、現状では「あったら便利だ」という程度のものが中心であると考えています。しかしながら、今のお話を伺うと、すでに“なくてはならないもの”になりつつあるという印象を受けました。実際のところはいかがでしょうか。
山口:ワークステーションに関しては、臓器の抽出などの分野でディープラーニングを用いたAI技術が当たり前になっています。
現在はワークステーションだけでなく、CTの撮影領域にも次々と導入が進んでいます。
患者さんをカメラで認識し、撮影の自動化をできる限り行う方法や、撮影された位置決め画像から臓器を正確に抽出して、さらに詳細な撮影範囲を決めていくといった形です。
冠動脈CT、心臓CTに関して申し上げますと、冠動脈はなかなかしっかり止まっている画像を得ることが昔から非常に困難でした。しかし、AI技術の導入によって、これまで技術者のノウハウが必要だった部分でも、より簡便に行えるようになってきています。この点は非常に助かっています。そうした進展も含めて、検査全体のスループットも上がってきていると感じます。
岡本:ありがとうございます。非常に前向きに受け入れられているということを強く感じました。例えば大腸CTでは、送気や技師さんの技量が良い画像を得て良い診断をする上で重要な要素となるかと思います。その点、冠動脈CTや心臓CTにおける技師さんの技量がどの程度の割合を占めているのか、そこでのAIの役割についても教えていただけますと幸いです。
望月:実は当院では、大腸CTも多くの件数を行っています。心臓CTと大腸CTには似ている部分がありまして、大腸CTでは送気の方法が重要になるかと思います。一方、心臓CTでは造影剤を使用するため、必要な分だけを注入したり、その量を判断したりするのが、技師の腕の見せどころなのかと思います。
AIの活用という点では、今後は撮影した画像に対して、成功しているかどうか、造影剤が過剰に入っていないか、あるいは最適な量であるかを評価することが求められてくるのではないかと考えています。
課題の焦点:教育・標準化・体制整備
島原:ありがとうございます。本当に勉強になるお話ばかりだなとお聞きしていました。
そのうえで、現時点での課題について改めてお聞きしたいと思います。
教育面なのか、技術そのものの成熟度なのか、それとも受け皿となる運用体制の部分なのか。
この“いまの課題感”について、望月先生、山口先生それぞれのお考えをお聞かせください。
望月:私が考える課題の一つは、検査から得られる情報の標準化かと思います。その背景としては、CTの技術精度が年々向上してきており、循環器内科医がいない施設でも、心臓CTの撮影が可能になりつつあります。さらに、日本循環器学会のガイドライン変更で、心臓CTの適応範囲が広がったことで検査件数自体も増加しています。
その二つの背景によって撮影自体は可能ですが、画像解析さらには読影というものの標準化のばらつきが大きく増えていることが、日本における課題ではないかと考えています。それに対してAIを使って標準化を行うことができれば、検査自体に求められることも最適化されていくのではないかと考えています。
山口:大事な部分を望月先生が指摘してくれたと思いますが、我々は現在、より分かりやすい情報、画像を先生方に提供しようと日々努力しています。しかし、実際に当院では様々な病院から紹介患者が来ており、各施設で撮影された冠動脈CTの画像が集まってきますが、これが施設によって全く内容が異なるという状況です。
それぞれの施設で慣れ親しんだ画像を提供されているとは思いますが、必要とされる情報は施設ごとにさまざまで、この標準化が一切なされていないという点は、私も非常に大きな課題だと考えています。
今後は、先生方と一緒に一つの方向性を示していく必要があると考えております。
製品紹介:冠動脈CT解析AI「Careverse™ CoronaryDoc」
島原:数が増えてきたことで、標準化やさまざまな課題が見えてきたと感じております。そのような中で、クレアボ・テクノロジーズ様ではいろいろな製品を取り扱う中で、この分野の課題を解決する製品も展開されているとお聞きしてます。こちらの製品についてもご紹介いただければと思います。
奈良:弊社には昨年末にリリースいたしました冠動脈CT解析AI「Careverse™ CoronaryDoc」がございます。
先ほども山口先生、望月先生からお話がありましたが、冠動脈CT解析では技師の撮影自体も大変ですし、その後の画像作成においても多くの処理を行っていただいております。例えば心臓のボリュームレンダリング画像や、CPR画像と呼ばれる画像作成を行っており、それらはすべての冠動脈に対して作成しています。
さらにこちらの各血管に対して石灰化や狭窄の確認を行っており、それらを最終的にレポートとしてまとめております。従来、このプロセスにはおおむね30分ほど、複雑な症例ではそれ以上の時間がかかると言われています。
弊社が販売を開始いたしましたCareverse™ CoronaryDocでは、画像生成・狭窄/プラーク識別・レポートといった作業をソフトウェアが3分以内に完了いたします。CT撮影が終了したら、データがソフトウェアに届くと僅かな時間で処理結果を表示可能となっており、待ち時間もありません。
こういった処理がAIによって行われていることを確認していただきましたら、こちらの作成された画像レポートはPACSなどのシステムにすぐに配信可能となっております。
こういった作業は、読影レポート作成の時間短縮にもつながることが可能となっております。
また、AIによる処理となりますので、一貫性の高い解析結果が得られることもメリットかと存じます。こちらの製品は、サーバーを施設内に設置させていただき、オンプレミスで作業が可能となっております。院内最大20端末から同時アクセスが可能となっておりますので、放射線科の技師様・ドクター、循環器の先生方による画像参照や患者様へのご説明にも幅広く活用できるソフトウェアとなっております。
導入現場の評価:スピード・精度・運用性
島原:そういった啓蒙活動や共有活動も行われており、日々の臨床においても当日に結果を返されている山口先生や望月先生にとっても非常に有用なツールであると考えています。実際に使用されてみて、良い点もあると思いますが、悪い話や今後の課題も含めて、率直なご意見をいただければと思います。
山口:当院での導入のきっかけとしては、放射線科医から検査全体のスピード、特に読影スピードを高めたいと要望があったことでした。そこで「Careverse™ CoronaryDoc」を紹介させていただいたところ、ぜひ導入したいとなり、導入に至りました。
特にオンプレミスで運用できることと、ウェブブラウザーで運用できることが非常に良かったと考えています。どこでもチェックできるということもありますが、これからの一つの使い方としては、CTガイドPCIも注目され始めています。
当院では日々、ドクターがカテーテルの患者にどんな治療をするかをプレゼンをしています。そのため、前日までに我々が作った画像をもとに病変長や血管サイズ、石灰化の分布などを確認しています。こういったものが、Careverse™ CoronaryDocを導入することで、循環器の先生が自由に計測系をどこでも行えるようになるのではないかと期待しています。
特に我々が重視しているのは血管抽出の精度です。血管の中心を正確に捉えることは非常に重要な作業ですが、現在使用しているシステムはワークステーションと比較しても修正の頻度が少なく、高精度だと感じています。
血管の抽出範囲についてですが、当院の320列CTでは超高精細のディープラーニング再構成というPEAKという機能が搭載されています。この機能との相性が非常に良く、末梢の非常に細い血管まで抽出できています。非常に低ノイズで空間分解能の高い画像は、相性が良いのではないかと考えています。
今現在CTの画像は高精細化されてきており、そのベースとなるDICOMの画像も512マトリックスから1024マトリックスに変化しています。これにいち早く対応していただいていることも、今回の導入のきっかけの一つです。
現在は放射線科医の読影支援という形で運用していますが、今後は救急で行われる冠動脈CTにもうまく活用できるのではないかと考えています。
最後に、日本の冠動脈疾患診療において、このシステムは非常に有効なものになるのではないかと考えています。
私が住む北海道では、医療過疎は深刻な問題であり、冠動脈疾患の発見の遅れが致命的になるケースが多いのが現状です。PCIできる施設も少なくなっており、特にACSに関しては切迫した状況であると言われています。高精細なCTは日本の各地域に導入されていますが、それがうまく活用されていない可能性があります。
しかし、現場において冠動脈CTのスキルが徐々に浸透すれば、日本のACSの予後も改善できるのではないかという夢を持って活動しています。
この強力なパートナーとなるのが、「Careverse™ CoronaryDoc」のようなシステムだと考えています。専門施設でも十分に使いこなせるシステムですが、むしろ医療過疎地域にこそ導入されるべきものだと思っています。
島原:ありがとうございます。望月先生はいかがでしょうか。
望月:残念ながら当院はまだ「Careverse™ CoronaryDoc」を導入していないのですが、使わせていただいて感じたメリットは二つあると思います。
一つは、やはり画像解析の自動化と時間短縮です。
心臓CTの画像解析に慣れていない方の場合、一人当たりの解析にかかる時間がどうしても長くなってしまう問題がありました。循環器に特化した病院ではない施設にとっては、大きなメリットがあるかと思います。
もう一つは、診断精度の標準化です。
例えば、画像解析自体は可能でも非石灰化プラークが検出されていないなどの問題をCareverse™ CoronaryDocで識別し、医師が対象を特定できるといった標準化が図られる点は非常に大きいと感じました。
産業側の視点と今後の展望
島原:ありがとうございます。かなりポジティブなフィードバックも多くいただいたように思いますが、それを受けて山田さん、奈良さんいかがでしょうか。
山田:そうですね。課題や厳しいご意見も伺いたいと思っていたのですが、山口先生・望月先生が所属されている病院はしっかりとした体制を整えられており、その中で高い評価をいただけたことを嬉しく感じています。
私たちが全国で営業活動を行う中で、地域の病院から「技師の数が足りない」「施設基準を満たせない」といった声を多く聞きます。そうしたリソース不足のために、本来やりたい医療を提供できず、検査メニューを取り下げざるを得ないケースも少なくありません。
このソフトを使用することで、さまざまなことが可能になって患者様を救えるのではないか、現在赤字で苦しんでいる病院が新たに利益を出せる機会があるのではないかとお聞きしております。実際の導入事例はまだ少ないですが、これから様々な病院の評価をいただきながら、広めていければと考えております。ご評価いただきありがとうございます。
奈良:このような評価をいただきとても嬉しいです。私たちは日々このような製品の販売活動を行っており、引き続き国内でのご紹介を進めていきたいと考えながらお話を伺っておりました。また、私自身も医療AIを紹介する活動の原点として、地元が田舎であるため、地域の医療の質を上げていきたい思いがあり、このようなAIでその地域をよりサポートしていければと考えております。
非侵襲診断の未来と、平準化への期待
岡本:ありがとうございます。冠動脈CT、心臓CTの未来が本当に楽しみだと感じながらお聞きしておりました。先生方のコメントも非常にポジティブで、私自身もこの製品を見てみたいなという気持ちになりました。最後に山田さんの今後の展望として、製品アップデートの方向性やユースケースを含め、薬事戦略上のアップデートなど、今後考えていらっしゃることがあれば、教えていただけますと幸いです。
山田:シリーズで品揃えをしておりますので、様々な展開があるかと思います。この循環器・冠動脈CTでは、非侵襲な診療を皆さん追求されており、それを支援するようなソフトウェアがこの分野でどんどん開発されています。そのようなものに展開していきたいというのが一つの目標です。
さらに、診断の支援であり、治療方針を決めるデータをしっかり検出できるようなソフトウェアを、現在我々が提供している製品の上にアップデート、もしくはアップサイドとして載せていき、一つの同じユーザーインターフェースで使えるものを提供していきたいと考えております。この製品を開発されている本国ではそのような取り組みが行われておりますので、ご期待に応えられるように努力してまいります。
島原:先生方からも標準化についてお話しがあり、その中には専門機関での標準化もあれば、地域格差を埋めていくことへの期待もあったと思います。まさにそれがAIの本領を発揮するところであり、今日のお話は非常に綺麗なストーリーであったと感じました。
本日は循環器領域でご活躍の山口先生、望月先生、そしてクレアボ・テクノロジーズの山田様、奈良様をお迎えいたしました。最前線の貴重なお話をいただき、大変有意義な時間となりました。皆様誠にありがとうございました。
協賛:クレアボ・テクノロジーズ株式会社( https://www.clairvotech.com/)
参照論文:
Careverse™ CoronaryDoc
販売名: 心臓CT画像解析ソフトウェア CoronaryDoc
一般的名称: 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム
認証番号: 306ADBZX00046000
本製品による解析結果は必ず医師による確認を行なってください。必要に応じて修正する必要があります。
■配信ページ:
YouTube:https://youtu.be/ExkhJQcqWT8