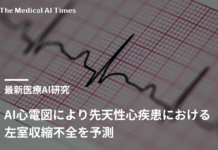腰痛症の治療方針は「患者の主観的な不快感の訴え」に依存し、根本的な解決とならない検査や治療につながりやすい。米国において腰痛症は糖尿病・心血管疾患についで第3位の総医療費という状況にもある。米オハイオ州立大学のチームは、腰痛治療の意思決定を強化するため、ウェアラブルのモーションセンシングシステムによる腰痛評価の研究を行っている。
Clinical Biomechanicsに掲載された最新の成果では、腰椎固定術を受けた121名の患者を対象に、「Conity」と呼ばれるウェアラブルモーションセンシングシステムを用い、腰部の3次元的な動きを定量化し、術前術後の疼痛と機能の評価を行った。Conityは上背部と腰部のハーネスに取り付けられたチップセンサーから、可動域・動作速度・加速度といった動作情報を取得する。あわせて被験者からは、疼痛・機能障害・回避行動・QOLを評価する質問票への回答を得た。その結果、モーションセンサーデータに基づく機能改善は術後6ヶ月まで見られなかったが、その後18ヶ月間にわたって機能が着実に改善していった。一方で、患者の主観的評価では、術後6週間という早い段階から疼痛・機能が著しく改善していた。
患者の自己評価とモーションセンサーによる客観的評価にタイムラグがあるという結果から、チームでは「痛みの軽減は重要な要素だが、手術後に通常生活に戻って安全かの判断には、客観的な機能評価がより有効」と考察している。研究を主導するMarras教授は「痛みについて患者は1から10までのスケールで主観的評価を求められる。しかし、椎間板そのものには痛みの受容体が無いことなどを考えると、その自己評価は何を意味するのだろうか。我々の技術は、患者が腰痛をどう感じているかだけではなく、動作がどのように異なり、生体力学の観点から何を意味するか定量的に測定するものだ」と述べた。本プロジェクトには米軍も関心を寄せ、腰痛を持病に抱えやすい航空機乗務員の脊椎機能評価に使用できるよう、国防総省が資金提供を行っている。
関連記事: