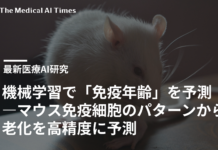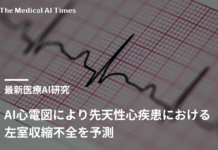近年、AI(人工知能)の活用は非常に多くの分野で急速に進み、AIに関する新しいニュースを見ない日はないほどだ。背景にあるのはDeep Learning(ディープラーニング: 深層学習)技術の発展だが、医療におけるAI活用ももちろん例外ではない。医療AIとは、AIという現代科学における無比のテクノロジーを臨床現場に取り込むものだ。一方、医療は人間の生命を直接的に扱う特殊領域であるため、AIがもたらす影響は他分野とは少し毛色が異なっている。今回は医療という文脈でのAIを広く説明し、AIとはそもそも何か、どういった利益を与えるものなのか、同時にどういった問題が生まれるのか、また、今注目すべき最新の医療AI動向についても紹介したい。
執筆者:Masaki Okamoto MD, MPH, MSc, PhD
信州大学医学部卒、東京大学大学院医学系研究科専門職学位課程および博士課程修了、英University College London科学修士課程修了。UCL visiting researcher、日本学術振興会特別研究員を経て、The Medical AI Times編集長。他に、米マサチューセッツ総合病院研究員、ハーバードメディカルスクール・インストラクター、TOKYO analytica代表取締役CEO、SBI大学院大学客員准教授、東京大学特任研究員など。専門はメディカルデータサイエンス。
1.医療におけるAIとは?
そもそもAIとは何なのか?
AI(Artificial Intelligence)は文字通り「人工の知能」を意味するが、その定義は研究者ごとに異なりあやふやなものだ。大まかに言えば、人類が行ってきた論理思考をコンピュータ上に再現するプログラムということになる。これまでは一定のルール下でしか答えを出すことのできない、非常に限られた「知能」であったが、2010年頃からの深層学習技術の高度発達により、プログラムは与えられたデータから自律的に学習することで判断基準を構築できるようになった。これは、人類には明確な基準を示せなかったものでさえ、AIは独自に判断基準を構築し分類できることを意味している。そして、この仕組みを医療に持ち込んだものが、いわゆる「医療AI」である。医療においては、単に疾患だけに注目しても、発症リスク評価・疾患診断・治療法選択・予後評価など多くの判断が必要になるが、個人ごとの状況の違いによって複雑化され、その判断は大抵とても難しい。集積された大量の患者データをもとに判断基準を構築し、例えば個人ごとに最適な治療法を提示してくれるとすれば、医療AIがもたらすメリットは患者・医療者の双方にとって非常に大きいことが想像できるだろう。
深層学習とは何か?
深層学習は近年のAI技術発達の根幹をなすものだが、文字通り日進月歩で新技術が公開されており、その全てにキャッチアップすることは難しい。ここでは、これらの基本となる用語の簡単な説明と、医療における活用例を示しておこう。
20世紀半ばから研究されているニューラルネットワークと呼ばれるアルゴリズム(手順を示したもの)がある。これは人間をはじめとした生物における脳神経細胞をモデルとしたもので、入力層・隠れ層・出力層といった層構造がエッジで結ばれた構造をとる。各層に関数を与え(活性化関数と呼ばれる)、エッジに重みを持たせることで、入力値を分類にかけ、答えを出力するための非常に複雑なモデルを実現している。この隠れ層が多い(深い)アルゴリズムを特に深層学習と呼んでいる。ちなみに機械学習は「与えられたデータから反復して学習し、適切な規則を見出す」ことを指し、深層学習もこれに含まれる。もう少し具体的に言うと、例えば、今の血糖値・血圧・体重の3点から1年後の糖尿病発症を予測するアルゴリズムを構築したいとする。多くの患者データを集めたデータベースから、血糖値・血圧・体重の3点を入力、1年後の糖尿病発症があったかなかったかを出力として設定することで、反復した学習を通してエッジの重みなどを決定する。できあがった最適なアルゴリズムは、この3点さえ与えれば、その人が1年後に糖尿病を発症するかどうかを予測できるようになる。このように入力と出力の関係を学習させるものを、特に教師あり学習と呼び、医療におけるAI開発では頻用されている。
一般的な機械学習では、特徴量(上記の例では血糖値・血圧・体重の3点)を任意で選択して投入するのに対して、深層学習では出力の決定に最も有用となる特徴量さえ自動的に抽出・学習することができる。代表的な深層学習モデルとして知られる畳み込みニューラルネットワーク(CNN)では、画像そのものを入力として与えるが、やはり具体的な特徴量を指定する必要はない。例えば米メイヨークリニックが開発したアルゴリズムの例では(過去記事)、心電図の波形画像そのものから、無症候性左室機能不全を識別している。もちろん心電図波形から特徴量を取り出し(波形の高さ・幅など)、同等のアルゴリズムを構築することもできるが、任意の項目を選び入力情報を限定してしまっている分(統計分野では「情報を捨てる」と表現する)、CNNによるアルゴリズムの精度を超えない可能性が高い。現在、このCNNが画像診断AI開発の主役となっている。
医療AIは強力だが万能じゃない
人工知能というとまさに人間の知能を模倣したもの、脳機能の代替物という印象を受けるが、これは多くの場合で過剰に捉えられてしまっている。わかりやすく言うと、現時点でのAIは「特定の何かを識別できるもの」であるに過ぎない。つまり、血管を画像から識別できるアルゴリズムであれば、動脈の画像を見せれば「血管だ」と返すし、毛髪の画像を見せれば「血管じゃない」と返すといった具合である。このアルゴリズムに何の改変も加えなければ、新生児と成人を区別することさえできない。したがって、今世間を大きく賑わせているほとんど全てのAIが、人間の「特定の非常に限られた機能」を抽出してコンピュータ上で再現しているだけということになり、要するに万能ではない。
ただし、この再現された機能があまりに強力なため、時として人類の識別能力を大きく上回るケースがある。例えば、電子カルテの記録から小児疾患を識別するアルゴリズムでは、インフルエンザを含む複数の疾患で小児科専門医の診断精度を超えたとの報告がある(過去記事)。この研究結果は、権威ある学術誌Nature Medicineで公開され話題を呼んだ。また、AIは人間の目では識別できない微細な変化までを捉えることができるため、悪性腫瘍診断など医療画像との親和性が高く、放射線科領域における技術発達が著しい(過去記事)。さらに、AIは安定した結果をもたらし続けることにも利点がある。特に日本の医療現場においては、人員不足による業務過重、夜間・休日の頻回な呼び出し、当直明け通常勤務、など医師の判断を鈍らせる過酷な現状がある。一定の出力精度を保ち続けるAIによるサポートは、医師にとっての一種の保険ともなり得るだろう。
2.AIの活用できる医療領域とは?

次にAIを活用できる医療領域をみていきたい。医療は大きく分けて、疾患の発症を防ぐ「予防」、既に疾患に罹患している人を見分ける「診断」、診断名を持つ人の転帰を改善する「治療」の3ステップがある。AIはこれら主要な3ステップのいずれにも貢献が可能なだけでなく、医療保険制度や医療提供体制を含む医療システムへの活用もみられるようになっており、あらゆる医療領域への活用が期待されている。この背景には、医療職の高度専門性に伴う人的リソース不足があり、AIに活路を見出そうとする国々は少なくない。
画像診断でのAI活用
放射線科、特に医療画像から疾患診断を行うプロセスは、医療AI活用の最たるものとして知られている。医療周辺技術の発達と高齢化の進展によって、施設あたりの読影を要する医療画像数は増加の一途だが、それに伴う放射線科医の増加は十分でない。AIは放射線科医の読影を助けることで、直接的に作業負担を軽減することができる。ただし、現状で正規の医療機器として承認を受けたAIデバイスは非常に限定的であることを知っておく必要がある。つまり、仮にAIが「悪性腫瘍がある」と診断したとしても、医師の確認なしに診断から治療に進むことは現時点でほとんどない。これは後述するAIの問題点にもなるが、アルゴリズムの妥当性の検証が不足していることと、AIを巡る法整備の遅れに起因しており、今現在、スクリーニングを除いた画像「診断」において正規に医師を代替する例は世界的にも稀有で、国内ではまだない。
一方で、健康診断における胸部レントゲン読影や心電図解析などは近い将来、AIによって完全に代替される可能性が高い。これはあくまで健康診断での画像読影がスクリーニングであり、後の個別受診で確定診断を得るためである。スクリーニングでは偽陰性(疾患があるにも関わらず「疾患なし」と判断されてしまうこと)が問題となるが、アルゴリズムの調整によって十分にこの問題を回避できる。不眠不休で安定した結果を出し続けることができるAIは、人手とコストの観点からも、この種のスクリーニング実施機関から前向きに受け入れられるだろう。英国・中国における眼科疾患スクリーニングの実用化例は、それぞれ過去にも紹介している(過去記事1・2)。
疾患診断でのAI活用
近年自然言語処理技術の急速な発達により、診療録(カルテ)解析がより一般的となった。結果的に診療録からの疾患診断AIは非常にその精度を高めている。過去に小児疾患の診断AIや(過去記事)、Amazonによるカルテ解析システム(過去記事)なども紹介したので参考にして欲しい。診療録は医師による所見の記載だけでなく、あらゆる検査結果・処方記録などが混在している。患者の病歴が長くなればなるほど診療録は膨大となり、優れた医師であってもその全てを限られた診療時間の間に捉えきることは難しく、患者の病態把握・他疾患リスクの把握などの面からもAIの利用が有効となるだろう。同様に、診療録だけではなく、生体センサーやモニター記録を統合したAIシステムの開発例もある(過去記事)。米フロリダ大学のこのシステムでは、集中治療室(ICU)における重篤な病態変化や致死的疾患の発生を予測するもので、まさにAIの有効な利用例と言える。さらに睡眠時無呼吸症候群など、診断に際して専門検査を要する疾患を、AIを利用することでより簡便に診断する手法の開発も進んでいる(過去記事)。
医療を巡る諸問題へのAI活用
AIの活用は実際の臨床現場におけるものにはとどまらない。医科学の信ぴょう性を揺るがすハゲタカジャーナル問題への活用や(過去記事)、スポーツにおけるドーピング撲滅に向けた活用(過去記事)、果てはバイオテロの防止に向けた取り組みにまで利用されている(過去記事)。
3.医療分野におけるAIの問題点・課題とは?

AIの妥当性検証が不足
医学研究者のなかには、AIアルゴリズムに対する懐疑的な目を向け続けるものも少なくない(過去記事)。アルゴリズムの示す高い精度にのみ目を奪われ、本質的な有効性が置き去りにされている、という意見である。
アルゴリズムの構築の際、一般的には1つのデータセットのみを利用する。このデータセットを例えば8割と2割のように二分し、片側をアルゴリズム構築用の学習セット、残りをテストセットとする。つまり、学習セットから導かれたアルゴリズムがテストセットでも同等の精度を発揮するか確認し、精度が保たれていれば妥当なアルゴリズムであると結論づけるやり方である。ただしこの方法だけでは、実は真の有効性は検証されていない。なぜなら、そのアルゴリズムは「ある特定の集団データ」から導かれたものに過ぎず、対象集団を変えてしまうとその精度は保たれない可能性があるからだ。分かりやすい例を挙げると、英国人を中心としたデータセットから得られたアルゴリズムは、日本人において有効であるとは限らないということである。実際、Amazonが誇る顔認識AI・Rekognitionは、「黒人の女性をうまく識別できないバイアスを持っている」との研究成果をもとにした一大騒動も引き起こしている(参照:米CNN)。対象集団を変えた多施設での解析、前向きの追跡研究など、従来の医学的エビデンス構築に基づいた精緻な検証が求められているのは間違いない。
医療AIを巡る法整備の遅れ
この5年ほどの間に、医療におけるAI活用は急速に進んだが、技術発展があまりに急であったため必要な法整備が遅れている。現実問題として、医療AIが示した診断結果をどう取り扱えば良いのかさえ十分な議論がなされていない。現時点では「必ず医師の確認を要する」との文言を付けることで、臨床現場などへのサポートシステムとしての導入がみられる程度にとどまる。本質的に有効なアルゴリズム構築のガイドラインを示し遵守させること、AIシステムが医療機器としての承認に受けるのに必要な要件、承認のないものへの一定の制限、などを明確化することは最低限求められている。有効性の不明な医療AIが、何の制限もなく市場に多く出回る状況は非常に危険である。
医療者のAIに関する知識不足
薬の効果・作用機序を知らずに処方することはできない。同様にして、医師をはじめとした医療者も、ある程度のAIに関する知識が今後必要となる。医学生の基礎教育としてAI科目の必要性が実際に議論され始めており、米ボストン大学の例を以前に紹介した(過去記事)。この先、医療におけるAIがさらに浸透し、あらゆる医療プロセスにAIが関与するようになれば(そしてそうなる可能性が高い)、医療者がAIを避けて通ることは非常に難しい。
また、2020-21年は新型コロナウイルスのパンデミックに対応するため、世界中の研究者が自身の研究フォーカスをこの新しい感染症へとシフトさせた。結果として、2020年1月の中国での発生報告以来、100日ほどの期間に実に2,000を超える関連プレプリント(査読前の学術論文でオンライン上に公開されたもの)が世に示された。通常の査読プロセスには長い時間を要することから、正式な学術論文として掲載されるにはその「即時性」をある程度放棄することとなる。新型コロナウイルス感染症のように、事態の推移が急速で、知見の共有に迅速性を要するケースではプレプリントの価値が高まる。また、プレプリントサーバーはオープンアクセスが原則となるので、情報の伝達・共有がよりスムーズとなる。
一方で、科学コミュニティは常に「査読を経ていない事実」への懸念を持ち続けている。本来淘汰されるべき「明確に誤った研究手法や再現不能な結果」などを含む論文が、常に一定数紛れ込むからだ。この非常時にあっても、価値ある研究成果を有効に伝達するためには、言葉尻に惑わされず確かな背景知識を持って冷静に読み解く姿勢が欠かせない。少なくとも「査読済み学術論文でさえ揺るぎないファクトを示しているわけでは決してない」ことを肝に銘じる必要があり、盲目的な研究結果の受け入れとその活用は時として大きな危険をはらんでいる。
医療AI関連研究もその根拠論文がプレプリントとして挙げられていることも少なくない。医療者は特に、プレプリントの特性を認識した上での適切な知見活用が求められている。
4.注目の最新医療AI動向

AIによる創薬
製薬大手のグラクソスミスクラインと英スタートアップ・Exscientiaは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の治療薬となり得る化合物を発見したことを発表している(過去記事)。
これはAIによる化合物探索プラットフォームを利用したもので、AI創薬の画期的な一幕になる可能性がある。従来のプロセスに比べると、AIを利用することで薬剤開発を大幅に効率化できるだけでなく、薬剤化できる可能性がありながら見逃されていたターゲットのあぶり出しにも有効となる。AIによる合成経路の自動探索技術については、以前にも紹介しているので参考にして欲しい(過去記事)。
2020年2月、上記Exscientiaと大日本住友製薬は、AIを活用して開発した新薬候補化合物の臨床第1相試験を開始することを公表した。AIによって導かれた化合物がヒトの臨床試験に入ることは、創薬における画期的なマイルストーンと言える。
死亡時画像診断への利用
死亡時画像診断という取り組みがある。死後のCTやMRI撮影から、死亡時の病態や死因を究明しようとするものだ(過去記事)。生体画像ですら人員不足が指摘されている放射線科医にあって、死亡時画像診断における読影までを強いることは現実的とは言えない。加えて、このような特殊領域の読影に長けた放射線科医はそれほど多くはない。こういった場面でのAI活用は極めて有用性が高いと考えられる。実際、AIによる神経変性疾患患者の死後脳MRI画像解析によって、新しい治療法開発につながる可能性も指摘されている。
医療機器への利用
伝統的な医療用ツールである聴診器にも技術革新の波は訪れている。StethoMe社のAI聴診器は、家庭での利用を目的としたEU認証の医療機器として知られる。患者の呼吸音異常を早期に捉え、AIによる診断結果と併せて臨床医に情報が共有されるシステムを構築している。StethoMeは2020年4月、欧州の主要な遠隔医療プロバイダー群との提携を公表しており、更なるシェア拡充が見込まれる(過去記事)。
採血手技をロボットに代替させようとする取り組みも始まった。米ニュージャージー州ラトガース大学の研究チームが開発した採血ロボットは、ディープラーニングを赤外線および超音波イメージングと組み合わせることで、組織内の血管を特定することができる。その後モーショントラッキングなど複雑な視覚タスクを実行し、針を血管に穿刺する。静脈が浮き出ていないような条件の悪い血管であっても、ロボットによる血管アクセスは88.2%の初回穿刺成功率が得られるなど、人の手技と同等あるいは上回っていくことが期待されている(過去記事)。
なお、2021-22年の医療AIトレンドは、ウェアラブルから「ウェアレス」への流れが加速するかもしれない。米ワシントン大学の研究チームは、スマートスピーカーを利用することで、物理的な接触を持つことなく心拍をモニタリングすることのできる機械学習システムを構築した。これは、スマートスピーカーから部屋に向けて「可聴域にない音波」を発することで、その反射音に基づいた心拍モニタリングを実現するもの。自宅で継続的に施行可能な低コスト検査であり、不整脈の早期診断・早期介入に繋げる画期的技術となる可能性があるほか、技術応用によって種々の医学的モニタリングがウェアレス化に向かう起点とさえなり得るものだろう。チームの研究論文は一読の価値がある。
医療で重要性を増す「エッジAI」
クラウドコンピューティングとIoT化はあらゆる領域で急速に浸透したが、近年はよりシステムの末端に近い場所(エッジ)でデータ処理を行おうという「エッジコンピューティング」が注目されている。現場に近いエッジデバイスにAIモデルを実装したものが「エッジAI」と呼ばれ、クラウドを利用せずエッジ側のみで学習から推論までの処理を完結するものも見られるようになった。
では、医療におけるエッジAI導入の利点はどこにあるのか。まず挙げられるのはネットワークの接続性を改善する点にある。つまり、あらゆる処理をクラウドベースで行うシステムに比較して、膨大な現場データの処理を部分的にエッジデバイスに負わせることにより、上位システムやネットワークに対する直接的な負荷の軽減につなげることができる。ヘルスケアの舞台はITインフラの発達した都市部だけではないため、特に医療過疎となりやすい僻地などにおいてもその有用性が際立つことになる。また、今後益々の発展が予測される遠隔診療やロボット手術においては、レイテンシーの厳密な制御が欠かせない。高度に要求されるその水準をクリアするには、エッジAIの活用が必要となることが容易に想定される。
遠隔医療の急成長
新型コロナウイルスの感染拡大を背景として、遠隔医療は急速な広がりをみせている。これまで医療画像読影を中心とした遠隔診断サービス程度に留まっていた遠隔医療は、次世代移動通信システムの発展やスマートフォンを始めとした高度情報通信機器の一般化・普及によって、その技術的課題のほとんどがクリアされた形となった。また、各国において遠隔診療を巡る法規制の見直しと緩和が進み、マーケットには遠隔医療を根幹事業に据えた新たなプレイヤーが乱立した。彼らの多くがプラットフォーム内にAI技術を取り込み、重症度判定や受診先選定、チャットボットによる問い合わせ対応など、フローの一部を技術によって最適化する試みを行う。
また、遠隔医療に伴う医薬品配送や検体回収にドローンを活用する流れもみられている。米シンシナティ大学の事例では、ドローンの医療利用を目指し、AIと一連のセンサーを組み合わせた自律飛行システム開発に取り組んでいる。現時点で、居間の入り口など屋内の雑然とした3次元環境でさえナビゲートできるなど、関連する技術開発への期待は大きい(過去記事)。
そういったなか、2021年3月にはAmazonが独自の遠隔医療サービス「Amazon Care」を展開することを明らかにした。発表直後は米最大手プロバイダーにあたるTeladoc Healthの株価が4%を超える下落をみせるなど、マーケットへの巨大な影響が浮き彫りとなった。Amazon Careはバーチャルケアと対面ケアを複合した医療サービスで、専用アプリを介した医師・看護師への相談のほか、必要時には医療従事者を個別に派遣する「往診」にも対応する。2021年夏からサービス提供を開始し、当初はバーチャルケアの全米50州での展開を進める。Amazonはアプリをエントリポイントと捉えた上で、現実の医療サービスとのハイブリッドを実現しようとする。在宅検査サービスの立ち上げに向けた交渉も始めている、とInsiderが報じるなど、医療相談・受診・検査・治療・経過フォローを含む全ての医療フェーズに関与する「包括システム」を狙う姿勢も垣間見える。