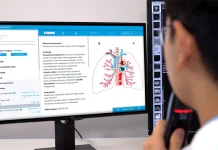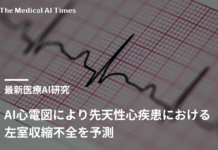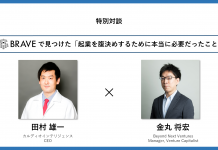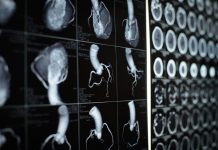医療とAIのニュース 2021
年間アーカイブ 2021
米Monogram Orthopedics – 個別化インプラントで人工膝関節置換術を変革
個別化医療が広く提唱される中、整形外科領域の手術では「既製品」のインプラントが今なお主流となっている。米Monogram Orthopedics社は患者ニーズに沿った個別の「ワンサイズモデル」インプラントを人工膝関節置換術向けに提供している。
Monogram Orthopedicsによる17日付プレスリリースでは、同社がクラウドファンディングで募集した3400万ドル規模のシリーズB資金調達において、参加投資家が5,000人を突破したと発表している。AI・ロボット工学・3Dプリントの基礎技術に基づき独自開発された同社製品は、2021年後半に人工膝関節置換術でFDA申請を予定している。
Monogram Orthopedicsによると、同社のインプラントは解剖学的により正確な挿入が可能で、微小な動揺については「競合他社のインプラントの方が最大630%多かった」と社内研究で示すなど、技術的優位性を強く主張している。患者のライフスタイルに適した、追加手術リスクが最小限の人工膝関節置換術のために、同社は追加調達資金によって技術の洗練と商業化を目指す。
関連記事:
「da Vinci Research Kit」が工学研究にもたらした恩恵と今後への期待
AI支援が変形性膝関節症の治療意思決定をより良いものにする
手術ロボットが人工関節置換を高精度化
終末期医療を支えるAIツール
医療には種々のフェーズがあるが、命のステージとして終末期に近づけば近づくほど、ケアの医学的な価値以上に「人生をどう考えるか」「どう生きたいか」という個別的価値観が重視される。今回は、この終末期医療を支えるAIツールを紹介する。
米ジョージア州に本拠を置く医療AIスタートアップのJvionは、がん患者の死亡リスクを予測し、早期の終末期医療導入に関する検討機会を与えるAIツールを提供している。「Jvion CORE」と呼ばれるこのAIツールは、3700万人を超える患者の診療記録と、各個人に関する4,500ものデータポイントを含む膨大なリポジトリとなっている。Jvionの機械学習アルゴリズムは、リスク推定を行う対象患者について、このリポジトリ内で類似した患者グループとマッチングさせることで、今後治療に対してどう状態が推移するかの「ケアジャーニー」を高精度に推定することができる。直近の研究成果によると、このAIツールが「今後30日以内に死亡するリスクが高い患者」を正確に予測することが報告されており、Northwest Medical Specialtiesを含む、米国内複数の医療機関において実臨床利用が進んでいる。
Jvion COREが興味深いのは、単に検査結果やバイタルサインに基づく生理学的要因から死亡リスクを推定するのみでなく、社会的孤立や医療資源へのアクセス不良、経済状況など、社会経済的因子を多分に含む点だ。開発者らは「これら社会経済的な健康の決定因子は、その多くが対処可能である」点を強調するとともに、臨床的リスク要因との抱合せによって、健康不良を規定する複雑な患者背景とその未来を描出しようとする。
Healthcareでは、Northwest Medical Specialtiesでの一症例を紹介している。乳がん治療中であったこの女性患者は、ある日Jvion COREによって「30日間死亡」のハイリスク者として抽出された。一方、臨床医らは彼女が経口化学療法によく反応し、状態は安定していたためにこの事実に驚いた。念のために来院を促し、採血を行って帰宅させたが、しばらくして「彼女が倒れた」との報告を受けた。実は尿路結石が背景にあり、敗血症に至るまでに進行していたのだ。入院の上、抗生剤投与で十分に回復し、再度自宅に戻ることができた。その後彼女は化学療法をやめる選択を取り、ホスピスケアに入って最期の時間を思うままに過ごし亡くなったという。
この事例はまさに最期の時間を「取り返した」一例と言える。医療のセーフティネットとして機能するAIツールが数多開発され、実際の医療システムに組み込まれる様子が日々報じられているが、そこには常に「人の生活」がある。AIによってもたらされる結果がどのようなものであれ、誰かを幸せにするものであって欲しいと誰もが祈っている。世界的に人の寿命が順調な延伸を見せるなか、終末期を豊かにする技術的取り組みにもまた、大きな注目が集まっている。
関連記事:医療AIの最新活用事例とは?医師が解説【2021年版】
野生動物の健康異常警告AIはヒトでのアウトブレイクも検知できるか?
野生動物の罹患率や死亡率の異常を早期に検出して、ヒトの新興感染症リスクの検知に活かそうとする公衆衛生学的な取り組みがある。米カリフォルニア大学デービス校の研究者らは、AIを用いて動物リハビリセンターへ入所する個体を分類する早期異常検出システムを試験している。
英国王立学会の学術誌 Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciencesに、同研究の成果が発表されている。早期検出システムには、カリフォルニア州内30の野生動物リハビリテーション団体で保護した動物に関する報告書(種類・年齢・入院理由・診断など)がリストアップされる。その報告書に自然言語処理を用いて分類し、特定の疾患や怪我に関する入院数のパターンを解析する。過去5年間で20万件以上の記録から「通常どれくらいの頻度」となるかについて基準が設定されており、これを超えた異常が検知されたときに専門家への警告が自動生成される。入所データが1~2日で処理されることで、個々の診断の確定よりも迅速に全体へのアラートが可能となるという。
1年間の試験で発せられた警告例として、痙攣症状の海鳥が貝由来のドウモイ酸中毒であったことや、ハトの神経症状が寄生虫Sarcocystis calchasiによるものと判明している。この早期警告システムがヒトの健康にも役立つ可能性として、ウエストナイル熱が一例として挙げられる。同疾患はアメリカ大陸では1999年以降に出現し、年間数千件の症例で致死率5~10%前後の人獣共通ウイルス感染症である。ウエストナイル熱は家畜や人間に感染する前に、鳥での流行が多いと考えられており、同種システムの活用でアウトブレイクが適切に事前検知されることが期待される。
関連記事:
ウシの結核を生乳サンプルからAIで識別
ライム病の初期皮膚症状を判別するAIモデル – 米ジョンズホプキンス大学
新型コロナウイルスの起源を探るAI研究
身体的魅力で収入が増加する「ビューティプレミアム」をAI研究が証明
「ビューティプレミアム(beauty premium)」と呼ばれる、身体的魅力と収入増の関連について多くの先行研究がある。しかし、外見の定義が主観的であることや、身長や体重など指標の測定誤差に課題があった。米アイオワ大学の研究者らは、全身の3Dスキャンデータに機械学習技術を適用して体型と世帯収入の頑健な統計学的関連を示した。
学術誌 PLOS Oneに掲載された同研究では、米国空軍が1998年から2000年にかけて実施したCAESARと呼ばれる調査プロジェクトのデータを用いた。データセットには全身のデジタル3Dスキャンなど各種身体測定値が含まれている。解析には、ディープラーニング手法のひとつグラフオートエンコーダが用いられた。結果、体型と世帯収入には有意な関連があり、さらにこれが男女で異なることを明らかにした。データ内の世帯年収の中央値7万ドルを基準にした場合、男性では身長が1cm増加すると世帯年収が約998ドル増加すると推定され、また女性の場合BMIが1減少すると世帯年収が約934ドル増加することが推定された。
これは、労働市場における身体的魅力のプレミアム効果が存在することをあらためて示すものであり、男女間でその効果の性質が異なるという従来の仮説をさらに補強する。著者らは、労働市場に関し(1)職場倫理・無差別研修を通じて差別意識を認識・改善する努力をすること、(2)ブラインド面接など採用・昇進プロセス全体でバイアスの侵入を最小化するメカニズムを奨励すること、を本研究の政策的含意としている。
関連記事:
パンデミック下における「遠隔医療利用の社会格差」
健康への社会的決定要因を評価するAI手法
50歳以上が直面する健康格差に立ち向かうプロジェクト – 米ハワード大学とAARP
小児入院患者に「ICUケアが必要となるか」を予測するAIモデル
米ジョージワシントン大学の研究チームは、小児入院患者において「直近でICUケアが必要となる可能性」を予測する機械学習モデルを構築した。研究成果はCritical Care Explorationsからオンライン公開されている。
研究論文によると、小児入院患者計4万人以上のデータを利用し、入院治療を受ける小児が「今後一定期間(6-12、12-18、18-24、24-30時間後)においてICUケアを必要とするか、ルーチンケアにとどまるか」を予測する機械学習モデルを構築した。予測因子は生理学的検査結果および現在の治療内容・強度とし、モデルパフォーマンスを独立したデータセットでテストしたところ、AUC 0.917と高い識別精度を示していた。また、興味深いことに種々のパフォーマンス指標は、シミュレートされた小児病院と、病床数やロケーション、教育状況などに差のある他医療機関においても同等であったという。
著者らは「ICUまたは非ICUケアとして、小児患者における将来のケアニーズを特定することは、疾患重症度の変化の推定であり、ケア要件が増加/減少/安定する患者をそれぞれ特定することができる」とする。疾患重症度予測における適切なフレームワークとして、特に「早期臨床介入の恩恵を受ける可能性の高い患者」を検出し得る点でその有用性を強調している。
関連記事:
小児静脈血栓塞栓症のリアルタイムリスク予測モデル
AIロボットRobinが小児科入院の孤独を和らげる – 米UCLA Mattel Children’s Hospitalの導入
熟練医が持つ「違和感」のモデル化 – 正常/異常のみのMRIスクリーニングシステム
ユーイング肉腫患者の5年生存率を予測するAIツール
医療AIの最新活用事例とは?医師が解説【2021年版】
BRAVEで見つけた「起業を腹決めするために本当に必要だったこと」
株式会社カルディオインテリジェンスは、心電図のAI自動解析システムを手掛ける医療AIスタートアップで、Beyond Next Venturesが主催するアクセラレーションプログラム「BRAVE」の卒業生でもある。
今回はカルディオインテリジェンス社CEOの田村雄一氏、Beyond Next Ventures社でBRAVEを主導する金丸将宏氏の対談の様子をお届けする(以下、敬称略)。
関連記事:Beyond Next Ventures – 国内最大級アクセラレーションプログラム「BRAVE」が見据えるもの
田村 雄一 Yuichi TAMURA
株式会社カルディオインテリジェンスCEO・医師。慶應義塾大学医学部卒。
心臓専門医としての目線から、臨床現場に本当に必要なAI医療機器を開発し社会実装するため、2019年に株式会社カルディオインテリジェンスを創業。
金丸 将宏 Masahiro KANAMARU
2006年株式会社東芝 (R&Dセンターに配属)に入社。次世代光ディスクの研究開発に従事。その後、セミコンダクター&ストレージ社に異動。クラウドサーバー向けHDDの企画・開発・製造をリード。2015年 DBJキャピタル株式会社に入社。テクノロジー系ベンチャー企業への投資・ 支援活動に従事。2016年3月にBeyond Next Ventures株式会社に参画。メディカル、エレクトロニクス領域を中心に投資活動に従事。東北大学大学院理学研究科卒修士、グロービス経営大学院MBA。
金丸:早速ですが、現在取り組まれている事業やプロダクトを、ご自身で始められたきっかけをお伺いさせてください。2019年に参加頂いたBRAVEの前になりますよね?
(編集部注:BRAVEは2016年に開始した国内最大級のディープテック特化型アクセラレーションプログラムであり、起業前/ 創業直後の技術系スタートアップの支援を行っている。約2ヶ月間に渡り、技術系スタートアップの成長のカギを握る経営チームの強化、専門家からのメンタリング、事業計画の作成支援、起業家・事業会社とのネットワーク等を提供し、短期間で資金調達可能なチームへの成長を促す。これまで102チームが卒業し、BRAVE卒業後の累計資金調達額は130億円を超えている)
田村:基礎的な研究を始めたのは2016年です。もう5年前です。金丸さんも昔会いに行かれた立命館大学の谷口忠大先生と私で、スタートしました。「実際にこのプロダクト開発をやった方が良い」と私自身が思ったきっかけとしては、私が臨床現場で難病を扱う中で、専門医の診療が届かない領域がフィールドとして非常に大きいと感じていた点です。治療に関してももちろんそうですが、様々な診断機会に関しても行き届かないところが、日本だけでなく発展途上国を中心として世界的にも多い。一番基礎的な検査である心電図や酸素飽度ですらそうです。その中で心電図や指先で酸素の取り込みをみる酸素飽和度のモニタリングがありますが、京都の会社さんと組んで最初に遠隔診療システムを立ち上げたのが2015年です。遠隔診療を介して自身の診療領域の患者さんのサポートを行う中で、その外にある大きな医療ニーズの中で医療従事者のサポートを行い、医療を受けられない患者さんをできるだけ減らす、そのような社会を実現するためには、自動化とAIというのが一番必要と感じるようになりました。
谷口先生と最初にミーティングした際、データを投入して機械学習にかけて自動化するようなことは技術的に難しくないだろうと。しかしそれでだけでは、AIの意義はそこまで大きくない。さらに進んだ形で、AIを使うことで当日には現れていない病気の微細な兆候を見つけてあげるようなことができると、本当の意味でAIを使う意味がある。「未病診断」と僕らは呼んでいますが、すなわち医師が従来発見できなかったことをAIで見つけてあげることができれば、そこには素晴らしい価値があるなという結論が出ました。医療現場が少し楽になるだけではなく、「今までの医療機器では発見できなかった患者さんを早期診断し、治療の機会を与える」ということをやってみようというのが研究開発のスタートでした。
そこから、基盤となるデータ集めやAIのあらゆる条件設定なども含めて行いましたが、その時に谷口先生の紹介で高田智広さん(現(株)カルディオインテリジェンスCTO)と知り合いました。当初想定していた技術も試行錯誤を重ねる中、1年半ぐらいで私たちが思い描いていた形でAIアルゴリズムができあがったので、これは是非社会実装していかなければいけないと強く感じ出しました。
社会実装の方法にも色々あって、例えば心電計のメーカーさんにライセンス供与したり、共同開発したりなどが一般的な形です。しかし自分たちが思い描いた診断・治療の世界観を実現・普及させ、社会を変えていくためには、自ら起業して社会実装を進めていくという手段もアリだなと考え始めていた折、ちょうどBRAVEに出会いました。
金丸:今のお話を聞くとストーリーとして筋が通っていると感じましたが、実際にご自身でやろうかなっていうところが、一般的なドクターの思考回路とはギャップがあるのかもしれません。その点は違和感なく、例えば元々何かご自身で開発するというご計画、またはお考えがあったんでしょうか?
田村:そうですね。社会変革を起こす仕組みづくりは、初めに「えいや」と思い切ってやってみないとなかなかできないものです。既存のメーカーさんに委託すると、理想の形での社会実装が目指せないのではないかという課題感も抱いていましたし、やはり自分たちの手で成し遂げたいと感じていました。もちろん様々な医療機器メーカーさんや製薬企業さんなどと共同研究や共同開発などをやってきた経験から、連携することで助かった点は多くありました。一方、自分たちのアイデアをしっかり盛り込めることもあれば、企業さまの事情で方向修正を図らざるを得ない経験もありました。既存のメーカーさんの事情と、医療現場の未来をどう変えていくかという視点が必ずしも一致しない事も出てきます。その中でエッジの効いたものを新しく開発していくには、自分たちで起業するという選択肢もあってもいいのではと思いましたが、起業に必要な知識のすべてを全く知らないというのが私自身の課題でした。「技術はできたけど、じゃあどうしよう」と立ち止まり、数か月考えていたのがBRAVE参加前でした。
金丸:まさにそこにBRAVEがはまったのかな、と思いました。
田村:そういう振りなんです今の(笑)。
金丸:ありがとうございます(笑)。実際、BRAVEを運営している私から言いにくいところはありますが、「教えてもらえそう」とか「何か勉強になりそう」とかBRAVEに期待されている点はいろいろある一方、「BRAVEに参加しなくてもここは自分たちで何とかなる」などもあったと思います。実際に「ここはちょっと何をしたら良いかよく分からない」というポイントは具体的にどういうところでしたか?
田村:そうですね。一点は資金調達も含めたビジネス面ですね。そもそもスタートアップ企業自体がどのように動いているのかが全体像として分からなかった。本を読んだり、実際に事業をやってらっしゃる方の話を聞いたりすることはできます。でも、具体的にどういう手順をどういう順番でやらなければいけないかが分からなかったです。例えば資金調達であれば、銀行から借金するべきなのか、それともVCさんや事業会社さんから資金調達をするべきなのか、などです。事業性は事業計画がないと分からないじゃないですか。要するに短期で売上が立ちそうなら、借金してやってしまえばリスクも少ないし早い。一方で、プロダクト開発費用など製造販売前後に必要な資金を厚みを持った形で数値化してタイムラインを引くみたいなことは、医療者としての経験だけでは厳しいものがありました。そういった意味での具体化とか精緻化が全然できていないことが大きな課題でした。
金丸:事業計画の作り方とか、バリュエーションの方法などを解説されている本はありますが、確かに僕もこの仕事をする前は具体的・実務的な部分の想像がつかなかったです。
田村:自分の持っているものがどういうスピードで開発が進んで、市場へ展開でき、売上が立つのか。もちろん数字遊びのようにできることもありますが、実際に積み上げていく上では「出資者側はどのように事業を見ているか」ということをきちんと考える必要があります。自分たちのプロダクト、自分たちの事業に落とし込んだ時にどのように組み立てていくかという課題を解決するために、「アクセラレーションプログラム」というものが世の中にあるということを知りました。
金丸:話は少し変わりますが、BRAVEで学んでみて、「できそうだったら起業しようかな」という心構えだったのか、あるいは「いや、難しくても起業するんだ」という腹決めのようなものにまでなったんでしょうか?
田村:個人では難しい、またCTOがいたとしても開発者だけでは難しい、というのは感じていました。BRAVEに参加する前は、どのような人材が必要なのかすらよく分かっていなかったので、自分たちで勉強すれば何とかなるのでは、という気もしました。ですが、実際BRAVEに参加して「やはり自分たちの力だけでは何ともならない」と痛感し、一緒に起業してビジネス面を支えてくれる仲間を見つけないといけないと痛感しました。BRAVEに参加してはじめて「本当の創業に至るまでの課題」というのは何も解決していない状態であることを明らかにできました。課題がより具体化した中で、じゃあ起業の腹決めをするには仲間が必要だと感じたわけです。
金丸:BRAVEではILPという仕組みによって、創業メンバー候補の方と一緒に事業計画をブラッシュアップしていただきます。田村さんとしては「どういう人が仲間として良いか」というのは、変わってきた、または固まりましたか?
(編集部注:スタートアップ経営に関心があるビジネスパーソンを募集し(ILP)、2ヶ月のプログラム期間中に参加チームとのマッチングを行い、ワンチームとしてピッチ大会に向けた事業計画のブラッシュアップなどを行う。これまでに300名のILP人材が、BRAVE参加チームとのマッチングを実現。BRAVE終了後、実際にマッチング先のチームの創業メンバーとしてジョインしたり、スタートアップへ経営陣として参画したケースも多数ある)
https://talent.beyondnextventures.com/ilp
田村:自分たちのプロダクトの意義を理解してくれる、社会的意義に共感してくれるというのがまず前提条件です。当然リスクの高い転職になるので、会社の取り組みと可能性を一緒に信じてくれる必要もあります。また、「自分たちが持っていない要素を持っている方」という点も大事だと思います。具体的には、実際に薬剤や医療機器に取り組んだことがあるとか、医療現場でマーケティングをしたことがあるとか、実際にその戦略を立てたことがあるといった経験は貴重ですし、医療現場での経験がないとしても、実際に責任ある立場でマネージメントの経験がある方が理想的ですよね。
金丸:実は今年もBRAVEを開催しており、本年は春と秋とで2回開催です。春は11チーム採択させていただきましたが、まさに事業計画をブラッシュアップしているところです(2021年7月の取材時点)。秋はこれからです。ILPの方々も募集をかけて、結果たくさんの方に集まってきてもらっているところですが、現在の田村さんとしては、0→1に関わっていただくメンバーとして重要な要素はありますか?
田村:やはり「何らかの事業を自分で責任をもって完遂した経験があるかどうか」ですね。そこはすごく大事です。責任者でなくともよいですが、ある領域に関してスタートからゴールまで設定したものを完遂したことがあるという経験があれば、どの業界でもその経験は適用可能だと思います。言われるがままにやってみたらできた、のような成功体験があることもビジネスパーソンの育成では大事ですが、成功した裏で何が動いていたかを真には理解していない可能性がある。僕らも多くの方と一緒に仕事させてもらっていますが、やはり一貫した完遂経験のある人は強いと感じます。
金丸:リーダーシップの経験があると口で仰る方はいますが、実際のところは0→1で差がでますよね。
田村:そうなんですよね。例えば大きな会社の一つの事業部で既に実績が出ているところを引き継いでやるケースだと、0→1の局面で力を発揮できない可能性もあるとは思います。
金丸:シリコンバレーのように、起業の経験が比較的得やすい環境であれば別ですが、今の日本のようなそのような経験をする機会がない中で、たった2ヶ月のBRAVEの期間だけでも、事業の0→1をリーダーシップを持ってなんとか経験してほしいなと思い、ILPというプログラムを導入しています。
田村:ILPの皆さんにとっても素晴らしい経験値になると思います。実際に創業から事業化までをシミュレーションする中で、面白いと感じて飛び込んでみたいとなった時に、自分が売りにできるポイントがどこにあるのか。会社での肩書やポジションを外した時、何が残るのかを自分で見つめ直す機会は、会社の中だけではそうそう得られないかもしれません。その意味でもILPはすごく良いプログラムなんじゃないかなと思います。
金丸:ありがとうございます。話は変わりますが、田村さんは起業して丸2年でしょうか?
田村:この10月で2年ですね。
金丸:起業すると決意してからは5 年という時間が経ちましたが、事業を構想していた当時の田村さんご自身、あるいは、これから今BRAVEに参加しようとしているチームに向けたメッセージはございますか?
田村:事業化はそんなに簡単じゃないということ、そして、仮にいいシーズを持っていたとしても、それを受け入れる市場や、その魅力を伝えるような手段が無ければ浸透はしないということです。シーズが技術的に優れているとか、社会を変え得るといったことは最低条件ですが、それだけでは市場では勝てないという点は、僕らが直面している課題です。マーケティングにしても販売戦略にしても市場戦略にしても、これらをどのように組み立てていくかを一緒に考えてくれる人が必ず必要だということは伝えたいです。
金丸:BRAVEで事業プランのブラッシュアップをする中で、良い戦略が作れない、「海外から参入者が来たらどうするか」など、過剰にリスクを考えるようになることがよくあります。完璧な事業プランが浮かばない、または考えすぎてしまい「事業への熱」のようなものがシュンとなくなるケースが、若い人に多いんです。事業そのものや事業プランに迷っている人が仮にいたとして、いろいろ考えないといけない中で、まだ0の段階の人向けに、お伝えしたい「必要条件」のようなものはありますか?
田村:起業では事前に予想したリスクよりも、予想できないことのほうが遥かに多いと思います。だからこそ事前に予測できないが起きた時に「やり抜くことができるかどうか」がすごく大事かなと。逆に言うと、やり抜く仲間と気力があれば、事業がピボットするにしても、起業自体は決してひどいことにはならないと思います。まずは自分たちが持っているプロダクトを信じる一方で、社会実装していく上では必ず困難があるということを理解しておく必要があります。
また自分たちでは全くコントロールできない困難というのがあります。僕らも創業して「資金調達をしようか」という時にコロナがきました。コロナが拡がり始めた瞬間は社会全体がシュリンクしました。事業者さんからの投資が冷え込む可能性を懸念して、VCさんも「既存の投資先を生き残らせるためにどうするか」というところがメインになってしまった。ちょうど創業してお金を集めようとしたタイミングに、これがぶつかってしまったわけです。このように自分たちがコントロールできない、事前に予測していない困難は何らかの形で必ず起きてくると思います。そういった時にも自分たちのプロダクトを信じてやり抜けるかどうかがすごく大事ですね。ですから、「いろんなことが起きるとストレスだな」と思う人は、正直やめておいた方が良いと思います。
金丸:田村さんは臨床現場におり、ここにペインがあるよっていうのを田村さんご自身がよくわかっていたので、プロダクトの可能性を信じられたのはかなり大きかったでしょうか。
田村:開発しているプロダクトが今現在、現場にないわけですからね。
金丸:医療系のスタートアップの中で、若いドクターの方が創業されるケースが多いです。弊社の投資先でいえばアイリスの沖山さんや、CureAppの佐竹さん。臨床のご経験がある方が事業をやるというのは、医療現場のペインを外さないという点がすごく大きいなと思っています。田村さんはドクターの方が起業されるのをどう思いますか?
田村:万人に勧めるというのは語弊がありますが、でも臨床現場のペイン、特に専門医や広く現場を見ている医師や医療従事者にとってペインというのは、確実に現場に存在するもので、それはものすごい強みになります。それを自分の力で解決したい方には是非やってもらえればと思います。
金丸:外から見ると医療現場は想像でしかないですし、経験できないものです。そのような中で、現場の声が分かって、開発力もあるチームは強いなと思います。
BRAVEの話に戻りますが、実際に参加されてみて、BRAVEには、さらにこういうのがあった方がもっと良いんじゃないかというのありますか?
田村:BRAVEはアクセラレーションプログラムとして非常に完成されていると思います。ILPの方がBRAVEを終えられた後「実際に飛び込むケース」があった時にどのようにサポートするのかは大事なポイントかなと思います。ILPにとっての出口戦略みたいなものが、より現実的なサポートとしてあるともっと良いかなと思います。そうすれば、BRAVE参加での創業体験から実際の事業化プロジェクトに参加するまでが一体化するはずです。ILPの方の中でも「一歩踏み出せない」時に、サポートする事後プログラムのようなものがあれば、スタートアップに飛び込む人も増えていくかなと思います。また実際に起業家になるためには、その事業を知るだけではなく、「あなたに何が必要か」を教えてくれるとか、振り返ることができるようなプログラムがあれば、さらにマッチングがうまく機能するかもしれません。
金丸:貴重なご意見です、ぜひ参考にさせていただきます。本日は貴重なお時間を頂き、誠にありがとうございました。田村さんの益々のご活躍も期待しております。
田村:こちらこそありがとうございました。
【関連リンク】
ディープテック特化型アクセラレーションプログラム・BRAVE
クリニカルゲシュタルト – 見た目で疾病罹患を識別するAI
臨床家にとって視覚情報は重要な意味を持つ。「患者の顔つきのみから疾患を推定できることも十分にある」というのは熟練医のコンセンサスが得られるところでもある。近年、このようなゲシュタルト診断を「AIアルゴリズムによって再現・高精度化させる取り組み」が多方面でみられている。
オランダ・フローニンゲン大学医療センターの研究チームは、合成画像によってトレーニングした深層学習アルゴリズムが、顔画像によって疾病罹患者を識別できる可能性があることを明らかにした。Frontiers in Medicineからこのほど公開されたチームの研究論文によると、Chicago Face Databaseに登録されている126枚の健常人画像を用い、うち26枚を画像加工によって急性疾患の罹患者様顔貌に修正することでモデルの学習を行った。さらに22名のボランティアを対象として、リポポリサッカライド(LPS)を投与し、敗血症症状を再現した上で、投与前後の写真によってモデルの性能を検証した。結果、顔貌からの疾病罹患者識別において感度は100%を達成しており、除外診断ツールとしての有用性を示していた(感度が高い検査では偽陰性が少ない。本例で言うと、実際は疾病罹患があるにも関わらず「罹患無し」と判断されてしまうケース(偽陰性)は少ないことになるので、陰性結果をもって高確率に「罹患無し」と推定できる)。一方、トレードオフによって特異度は42%にとどまっていた。
研究者らは「顔写真の合成拡張データセットを用いて学習した深層学習アルゴリズムは、健康な人と模擬的な急性疾患の人を区別し、大規模データセットの入手が困難な健康状態に関するアルゴリズム開発に、合成データを使用できる可能性も示した」としている。クリニカルゲシュタルトへの新たなエビデンスを加えるとともに、利用可能なリアルワールドデータの不足しがちなヘルスケア領域において、AI構築に際する示唆的な研究成果と言える。
関連記事:
ぼやけた顔画像を60倍以上シャープに – 敵対的生成ネットワークによる革新的画像処理技術
豪PainChek – 表情分析AIアプリで認知症高齢者の痛みを代弁
脳卒中の迅速診断をスマホ動画で行うAI研究
ヘルシンキ大学 – 頭に浮かぶイメージを画像化するAIテクノロジー
医療AIの最新活用事例とは?医師が解説【2021年版】
救急外来で心房細動治療が見過ごされないためのAIアプリ
心房細動治療では、脳卒中リスクを低減させるため抗凝固療法が必要となる。しかし、実際の現場ではガイドライン推奨の治療が行われず見過ごされたり、不十分な治療にとどまるケースが一定数存在している。米Lucia Health Guidelines社は、ガイドラインに基づくケアのための臨床意思決定支援ツールを開発している。
Lucia Health Guidelinesのニュースリリースによると、同社が開発した心房細動治療の意思決定支援アプリ「Lucia AFib App」の概念実証研究結果が、学術誌 Journal of the American College of Emergency Physicians (JACEP) Openに発表された。研究では、機械学習アルゴリズムで心電図から心房細動を検出するLuciaのアプリが、救急部の循環器専門医以外に対し、ガイドラインに沿った治療開始を推奨できたかを検証した。アプリによって、対象患者297人のうち98.3%に適切な治療を開始できたのに対し、アプリなし(従来型の医師単独判断)では推奨治療に至ったのは78.5%であった。
Lucia Health Guidelinesの共同創設者で心臓電気生理学者であるGilAnthony Ungab氏は、彼の父親が未診断の心房細動で脳卒中を患った経験をもつ。Ungab氏によると「機械学習には、専門家不在の場での臨床を補うことに大きな可能性がある。今回の結果は、ERの臨床家がポイントオブケアでこのアプリを使用し、心房細動の治療・管理を改善できることを示唆する重要な検証マイルストーンだ」と述べている。救急外来は、低所得者やサービスの行き届いていないコミュニティに住む多くの米国人にとって重要なアクセスポイントであり、患者が脳卒中の一次予防を確実に受けるためのキーサイトともなっている。
関連記事:
Tempus – 心房細動発症を1年前に予測する心電図分析プラットフォーム
Volta...
BlueJeans Telehealth – Apple Healthアプリとの統合
Verizonは米国の最大手電気通信事業者として知られる。同社は昨年、法人向けビデオ会議サービスを展開するBlue Jeans Network社を買収しており、これを礎として、コロナ禍において遠隔医療サービス(BlueJeans Telehealth)へとその事業範囲を拡大した。Verizonはこのほど、同社の遠隔医療ソリューションにApple Healthアプリを統合し、新たな機能を付加したことを明らかにした。
Verizonが11日公表したところによると、Apple Healthアプリとの統合によりプラットフォームの利用者は、心拍数や心電図、睡眠、歩数、転倒など特定の健康データを医療者側とスムーズに共有することができるようになる。日常データは特定の疾患管理において臨床的価値が高く、通常の対面診療・臨床フローと比しても、同プラットフォーム利用が医療の質的向上に資する可能性もある。
McKinsey & Companyによると、2021年7月時点において、米国での「遠隔医療利用率」はパンデミック前の38倍レベルで推移しているという。消費者の40~60%が一連のバーチャルケアソリューションに関心を示すなど、新型コロナウイルスの感染拡大がもたらしたヘルスケアセクターへのインパクトは、医療の在り方自体を大きく様変わりさせている。
関連記事:
パンデミック下における「遠隔医療利用の社会格差」
Amazon Care – 忍び寄る遠隔医療業界の「Xデー」
耳の感染症を家庭で遠隔診療 – ジョンズ・ホプキンス大のAIスマート耳鏡「OtoPhoto」
ニューヨーク大学 – 在宅脳刺激による精神神経疾患の遠隔治療プログラム
医療AIの最新活用事例とは?医師が解説【2021年版】
早期肝細胞がん切除術後の生存率を予測するAI研究
肝細胞がんは、ハイリスク患者のモニタリングプログラムと画像診断技術の向上により、全体の40-50%が早期肝細胞がん(EHCC: early hepatocellular carcinoma)として診断されるようになってきた。EHCCは切除や焼灼による根治的治療で良好な予後が期待できる。しかし、肝細胞がんの予後を予測する病期分類は、EHCC患者の切除術後に焦点を当てていないため、その予測精度は不十分との指摘があった。
南京医科大学の研究グループでは、EHCCに対する肝切除後の生存率を予測する機械学習ベースのモデルを開発している。肝切除を受けたEHCC患者2,778名のデータから構築・検証された機械学習モデルは、年齢・人種・αFP・腫瘍径・多房性・脈管侵襲・組織学分類・線維化スコアといった8つの変量から構成されている。これは「10年後の疾患特異的生存率」についてc統計量 > 0.72という良好な予測精度を達成しており、AJCC分類のような既存の病期分類と比較しても優れたリスク層別化ができたという。研究成果は Journal of Hepatocellular Carcinoma誌に掲載されている。
同研究は、大規模データセットに基づく機械学習アルゴリズムをEHCCに初めて適用したものと謳う。著者らは「容易に入手できる診療データから学習したモデルによって、既存の予後予測情報を補完し、EHCC切除後患者の個別化治療を改善する可能性を示すことができた」と結論づけている。
関連記事:
AIによる肝細胞がんの予後予測 – システマティックレビュー
肝細胞がんに対する「機械学習ベースの臨床的意思決定支援システム」
声無き声を聞き分ける – 肝細胞がんの予測モデル
耐性菌の迅速検査に向けたセンサー開発
抗菌薬の過剰投与から細菌の耐性が高まり、世界の医療システムに負担をかけている。現行の抗菌薬感受性試験(AST: Antibiotic Susceptibility Test)はコストが高いことに加え、結果処理に最大48時間かかるという時間的制約もある。カナダのブリティッシュコロンビア大学オカナガンキャンパス(UBCO)では、迅速で費用対効果の高いツールとして、抗菌薬耐性を測定するマイクロ波センサーの研究開発に取り組んでいる。
UBCOのニュースリリースによると、同研究ではマイクロ波を高感度に測定する空洞共振器を用い、寒天培地上で培養された大腸菌に抗菌薬エリスロマイシンを投与した際の振幅を測定している。抗菌薬なしで菌が増殖する場合は15時間で最大0.07dBの振幅変化があるが、抗菌薬で増殖が抑制されると振幅変化は0.005dBに留まった。このセンサーによって6時間以内に「感受性の決定的な結果」を示すことができるとして、迅速かつ高感度な耐性菌検査への応用が期待されている。研究成果はScientific Reports誌に掲載された。
視覚的に自明となる前に「細菌の成長を区別」することで、抗菌薬の投与量や種類を調整するリアルタイムな個別化治療への道が拓かれる。研究を主導するUBCOのZarifi氏は「抗菌薬耐性を獲得する細菌側の進化が喫緊の課題だが、センサーや診断技術の適応は後れを取っている。医療従事者が自由に使えるツールが増え、抗菌薬の不適切使用を減らし患者ケアの質が高まることを、私たちは最終的な目標としている」と語る。研究グループは次の段階として、センシングデバイスにAIを統合したスマートセンサーを開発することを目指している。
関連記事:
抗菌薬は魔法の薬ではない – アフリカでの抗菌薬濫用を防ぐAIツール
多剤耐性結核にAIプラットフォームで取り組む – InveniAI社のTBMeld
抗菌薬の正しい使い方を教えてくれるAI – 尿路感染症治療は個別化の時代へ
「AI x バイオ」で医療を変革 – ネクスジェン株式会社代表インタビュー
「どこが痛むか」が疼痛の転帰を予測する
ボディマップに沿って報告された痛みの分布が、痛みの質や強さのみならず、3ヶ月後のアウトカムにも関連していることを米ピッツバーグ大学の研究チームが明らかにした。研究成果はオープンアクセスジャーナルのPLOS ONEから公開されている。
本研究論文によるとチームは、2016年から2019年にかけて7つのペインクリニックを受診した患者2万名強のデータを解析し、この成果を導いている。全ての患者に対し、自身の疼痛部位を図面上で指し示させ、体表面74箇所に分類した。一般的なクラスタリング手法である階層的クラスタリング(hierarchical clustering)を用いたところ、疼痛分布は9つのサブグループに層別することでき、これらによって医学的特性や疼痛強度、疼痛の質、アウトカムの差異がみられていた。具体的には「首・肩」のグループにおける疼痛強度は「首・肩・腰」のグループより小さく、最も疼痛強度が高いサブグループは広い疼痛範囲を持っており、これは身体機能低下・不安・抑うつ・睡眠障害との独立した関連を示した。さらに3ヶ月後のフォローアップ調査では、いくつかのサブグループに疼痛と身体機能の改善がみられたが、最も高頻度な改善を示したのは「腹部」(49%)で、逆に「首・肩・腰」では37%の改善にとどまっていた。
研究チームは「痛みの分布が疼痛管理の個別化に重要な役割を果たす可能性がある」とした上で、慢性疼痛の身体的分布を「どのように伝えるか」がその後の疼痛および身体転帰を強力に予測し得る事実を強調する。主観的要素の大きい疼痛において、その表現型にフォーカスしたユニークな研究成果が、医学的知識体系に新たなエビデンスを加えた。
関連記事:
愛猫の痛みを教えてくれるAIアプリ「Tably」
AIによる高齢者の疼痛評価
痛みを数理モデルで解釈する
医療AIの最新活用事例とは?医師が解説【2021年版】
胸部CT画像に基づくCOVID-19患者の予後予測AI
COVID-19患者の管理において、疾患の進行と死亡率の迅速かつ正確な評価が欠かせない。米マサチューセッツ総合病院(MGH)の研究チームは、胸部CT画像からCOVID-19患者の予後を直接予測する「教師なしAIモデル」を構築した。本チームは先行してScientific Reportsから公開した研究論文の中で、教師ありAIモデルによって胸部CT画像からCOVID-19患者の予後を予測できることも示していたが、教師なしとした今回のモデルでは、その構築に「アノテーション作業」も不要となり、画像単独に基づくエンドトゥーエンドの高精度な生存分析モデルを実現した形となる。
Medical Image Analysisからこのほど公開されたチームの研究論文によると、モデルの根幹に教師なしAIを用いることで、定量的画像解析よりも高い精度で、患者CT画像から直接予後を予測することができるという。これは、敵対的生成ネットワーク(GAN)によって胸部CT画像から直接的に生存時間の推定を行うことを可能とする「pix2surv」と呼ばれる新たな予後予測モデルを提案するもの。これにより、このモデルでは、従来の殆どの画像ベースの予測モデルでは不可能であった、患者固有の生存時間を予測できる。MGHの3D Imaging Researchチームを率いる吉田広行・研究ディレクタは「この教師なしAIモデルは従来手法に比べ、大幅に高い予測精度と低い予測誤差を持つ」と述べるとともに、研究チームでは現在「本モデルが他疾患にも拡張可能」と考え、その可能性を模索している。
1811年に設立されたMGHは、ハーバードメディカルスクール最大の教育病院として知られる。Mass General Research Instituteは、米国屈指の病院ベース研究プログラムを展開しており、年間研究活動費は10億ドルを超え、30以上の研究所・センター・部門で働く9,500名以上の研究者によって構成されている。
関連記事:
COVID-19リスク因子と死亡予測AIモデル
救急科AI – COVID-19の増悪を予測するマルチモーダルAIシステム
COVID-19画像診断の機械学習モデルは臨床レベルに達していない?
COVID-19を巡る臨床的意思決定を支援するAI
YouTubeがCOVID-19に関する誤情報を拡散させる可能性
AI手法で示された乳がん予後予測の鍵「コラーゲン配列」
乳がんは米国女性の死亡原因第2位であり、早期がんに対する有効な予後予測バイオマーカーの確立とそれによる適切な治療戦略策定が求められてきた。米ケース・ウェスタン・リザーブ大学のグループは、AI手法で乳がんの治療後再発を予測するバイオマーカーを特定する研究を行っている。
同大学のリリースによると、研究では早期のエストロゲン受容体陽性(ER+)浸潤性乳がん(IBC)において、生検検体のHE染色画像に機械学習を適用し、「コラーゲン線維の配列がER+ IBC患者の生存期間の予測に有用である」ことを示した。解析の中で、生存期間が短い患者では、コラーゲン線維の配列がより秩序立っていることが判明している。特殊なコラーゲン染色や顕微鏡読影を必要とせずに、汎用的なHE染色でER+ IBCの予後予測ができるバイオマーカーとして、構築されたモデルの活用が期待される。研究成果はnpj Breast Cancer誌に掲載された。
同研究では、逆に「コラーゲンの配列が乱れたり壊れていることで予後が良くなる」ことも示されている。同研究グループのひとりAnant Madabhushi教授は「コラーゲンの『高速道路』がひどい状態なら腫瘍の移動が難しくなるが、整理されていれば腫瘍のヒッチハイクは簡単になる」と例えて解説している。同手法により、高度な画像処理顕微鏡をもたない病院でも、単純な染色スライドのデジタル画像による乳がん予後予測が病理医の日常業務として確立されるかもしれない。
関連記事:
AI病理診断の雄「Ibex」 – 乳がん診断で欧州CEマーク取得
BreastPathQ Challenge – 乳がん画像分析で病理医を上回る識別精度を達成
乳がんの病理診断を説明可能なAI
統合失調症リスクを捉えるエピジェネティックマーカー
米ベイラー医科大学などの研究チームは、機械学習アプローチによって統合失調症リスクを示すエピジェネティックマーカーを特定し、統合失調症の有無を血液検査で高精度に識別できることを明らかにした。
生物科学における比較的新しい概念として「エピジェネティクス」がある。生命はゲノムに依存し存在するが、遺伝子発現を細胞がコントロールするプロセスをエピジェネティック制御と呼ぶ。塩基配列の一部がメチル化すると遺伝子の働きが制御される事実があり、DNAにおける「4種の塩基配列だけ」が遺伝子の働きを決定するのではないというもの。同大学が3日明らかにしたところによると、研究チームは血液サンプルに基づき、統合失調症の診断を持つ人と持たない人の間で異なるメチル基プロファイルを特定したという。この新しいエピジェネティックマーカーによって構築したモデルは、独立したデータセットでの検証において80%の精度で統合失調症患者を識別できたとする。
研究チームはsPLS-DAと呼ばれる機械学習アルゴリズムを用い、ヒトゲノムの特定領域(CoRSIV)を分析することでこの成果を得た。研究を率いたChathura J. Gunasekara氏は「我々の研究は非常にエキサイティングだ。人生の早い段階で統合失調症リスクを予測できる可能性を示しただけでなく、他疾患への適用余地も大きい新たなアプローチを提案している」とし、成果の重要性を強調している。
原著論文:A machine learning case–control classifier for schizophrenia based on DNA methylation in blood
関連記事:
法医学領域における年齢予測のためのエピジェネティックモデル
統合失調症患者の1親等以内の発症リスクを予測する機械学習モデル
デジタルフェノタイピングが精神疾患の分析を加速させる
精神疾患へのAI活用 – 機械学習アプローチによる長期予後の予測
精神疾患治療のアドヒアランス不良を検出するAIシステム
「転移リスクの高いがん細胞特性」を視覚化するAI研究
AIが識別する画像の微細な違いは、「ある特定の細胞の特徴」など、解釈困難な差であるためにその臨床利用も容易ではない。その課題克服のため、米テキサス大学サウスウェスタン医療センター(UTSW)の研究グループは、皮膚がんであるメラノーマにおいて「転移する可能性の高い細胞と低い細胞で視覚的に何が異なるか」をAI手法で明らかにする研究を行っている。
UTSWのニュースリリースによると、同研究は7人のメラノーマ患者の腫瘍サンプルから約12,000個の生きた細胞の動画を撮影し、約170万枚の画像を生成した。AIアルゴリズムによって画像から56種の数値特徴を引き出し、そこから転移性の高い細胞と低い細胞を識別するものを1つ特定した。この数値を操作することにより、転移リスクの高い細胞特性を誇張した人工的な画像を逆に生成した。その結果、細胞の突起物である仮足のわずかな延長および散乱光の増加が、転移性細胞の視覚的な特徴であることを示すことができた。研究成果はCell Systems誌に掲載されている。
研究の有用性を証明するため、研究グループは凍結保存していたヒトメラノーマ細胞を、研究成果に従って転移性を分類しマウスに移植した。その結果、転移性が高いと予測されていた細胞は容易に浸潤する腫瘍を形成し、一方で転移性が低いと予測される細胞は、ほとんどあるいはまったく浸潤しなかった。研究メンバーのDanuser博士は「がんやその他の疾患の重要な特徴をAIで識別することが可能になるかもしれない」と語り、研究発展に期待を寄せる。
関連記事:
EARN – 転移性乳がんのドライバー遺伝子を予測する機械学習アルゴリズム
AIの眼 – 膵神経内分泌腫瘍の転移リスク予測モデル
大腸がんのリンパ節転移を迅速に検出するAIモデル
進行性メラノーマに対する免疫療法での治療反応を予測するAI研究
アルバータ大学 – AI研究のための「健康情報解析プラットフォーム」
カナダ・アルバータ州エドモントンに所在するアルバータ大学はこのほど、ヘルスデータの管理・分析を行う新しいプラットフォームを立ち上げた。ビッグデータ・プレシジョンヘルス・機械学習などを主要なキーワードとして、関連研究推進のための強力なツールとなることが期待されている。
アルバータ大学が明らかにしたところによると、DARC(Data Analytics Research Core)と呼ばれるこの新しいプラットフォームは、ヘルスデータのプライバシー規制や医療システムにおける州の情報共有基準に準拠した、安全環境での高性能コンピューティングと機密データ保存を実現しているという。また、DARCは統計・データ可視化・予測モデリング・機械学習のためのスケーラブルなシステムであるSAS Viyaも備えている。この統合プラットフォームにより研究者は、ビッグデータ分析やAI開発に基づくe-ヘルスイノベーションを加速させることができる。
プロジェクトを率いるLawrence Richer研究担当副学部長は「ヘルスデータ研究のコンピューティングに関する重要な要件が一貫して満たされており、データ共有を促進する環境によって実際に多くのデータが共有できるようになるだろう」と述べる。直近では、アルバータ州保健局がテラバイト級の画像診断データをDARC環境に転送し、プライバシーを保護しながら研究向けの演算処理を実現するなど、その価値を発揮し始めている。
関連記事:
唾液タンパク質データベースが個別化医療を変革する
メイヨークリニック – AIと患者データを結ぶ新規プラットフォームを発表
Truveta – 米国における巨大データプラットフォームを構築
EU – 欧州最大の病理画像データベース構築へ
画像情報なしの電子カルテデータから肺がんリスクを予測
肺がんの検診として低線量CTによるスクリーニングが普及してきた。低線量CTの被曝・偽陽性・コストという課題から、検査の恩恵を受けやすい肺がん高リスク患者を事前に特定することが望まれている。台北医科大学などの研究グループは、画像情報なしの電子カルテ記録を用いたAIによる肺がんリスク予測を行っている。
Journal of Medical Internet Researchに発表された同グループの研究では、台湾の健康保険データベース200万人のデータを利用し、ニューラルネットワークによる肺がん予測モデルを構築した。用いられた情報は、年齢、性別、直近3年間の診断と投薬の履歴などで、慢性気管支炎やCOPDなど呼吸器疾患の既往でサブグループが解析されている。モデルの予測力を示すAUCは全人口で0.90、55歳以上で0.87を達成した。
開発されたモデルは1年以内の肺がん予測に優れた性能を発揮している。このような予測モデルで肺がんリスクの高い個人を事前に特定することで、低線量CTによるフォローアップ検査を受けるべき集団を絞り込むことが可能となる。高コストの診断介入の必要性を最適化することは、これからの高齢社会にとってますます重要な観点となり、AIの役割が拡大していくことが見込まれる。
関連記事:
EHRコホートを用いた肺がん予後予測
Optellum – 肺がん検出・管理のためのAIプラットフォーム
肺がん免疫療法への治療反応性を予測するAIモデル
スタンフォード大が展開する「AI研究向け大規模画像リポジトリ」
米スタンフォード大学のAIMI(Center for Artificial Intelligence in Medicine and Imaging)では、AI研究の積極推進のため「注釈付き医療画像データセット」を無償提供する大規模リポジトリを展開している。
スタンフォード大学が2日明らかにしたところによると、2年前に立ち上げられたAIMIではスタンフォード大学医療センターを中心として急速な画像収集を続け、現在100万を超える注釈付き画像を管理・提供しているという。研究者らはこれらを無償でダウンロードし、自由にAI研究に利用することができる。また、AIMIはMicrosoft AI for Healthとの協力で、よりアクセスしやすく自動化された新しいプラットフォームも立ち上げている。これにより、世界中の機関からの多数の追加画像を、効率的にホスト・整理することができるようになる。さらにここでは、研究者向けにクラウドコンピューティングも提供しており、機械学習インフラストラクチャの構築にあたって、ローカルリソースの大量消費を懸念する必要がなくなるという。
AIMIは画像分析だけではなく、AI医学研究のためのエコシステム構築を狙う。適切なデータセットを用いることで、単にピクセルデータの議論だけでなく、他の関連するマルチモーダルデータを含めて臨床的に有用な症例を横断的に探索できるようになる可能性もあるとする。センターでは9つのデータセットで100万を超える画像を有しているが、来年にはこの数は2倍になることを見込む。AIMIの副ディレクタであるMatthew Lungren氏は「医療データは公共財であり、世界中の研究者に開かれているべきという我々の考えを倍加していく」と述べる。
関連記事:
スタンフォード大学「Trove」- ラベル付きデータを要さない自然言語処理フレームワーク
スタンフォード研究 – 手術後の長期オピオイド使用を予測する機械学習アルゴリズム
スタンフォード大学 – 医療AIに関するオンラインプログラムを開始
スタンフォード大学 – 足首の外骨格システムで歩行速度を40%向上
スタンフォード大学...
米Qlarity Imaging – 乳房MRIのAI診断を現場に届ける提携戦略
遺伝子検査の発達により、BRCA1/2遺伝子変異のように、乳がんハイリスク者の効果的なスクリーニング手法が提唱されている。それらハイリスク者に対しては、乳房MRIが各種ガイドラインで推奨されているが、検査適応のさらなる拡大は読影医にとって業務負担の著しい増加ともなりかねない。米 Qlarity Imaging社は乳房MRIの診断補助AIを開発し、放射線科医のパフォーマンス向上に貢献しようとしている。
Qlarity Imagingの2日付ニュースリリースでは、同社の診断用AI「QuantX」を、英Blackford社のプラットフォームに統合する提携が発表されている。プラットフォームのマーケットプレイス上での展開によって、導入障壁・コスト・メンテナンス・サポートといった各種要件が緩和される。
QuantXは乳房MRI領域でFDA認可を受けた先駆けで、承認時の臨床試験では放射線科医の乳がん見逃しを39%削減し、診断精度を20%向上させたと発表している。Qlarity Imaging社CEOのJon DeVries氏は「放射線科医の燃え尽きの現状を考慮すると、技術的進歩が必要かという問いではなく、どのように導入すれば最大の価値が得られるかということが問題だ」と語る。そのような観点から、画像診断AIを開発する各社にとって、プラットフォームとの提携戦略がトレンドとなっている。
関連記事:
AI病理診断の雄「Ibex」 – 乳がん診断で欧州CEマーク取得
BreastPathQ Challenge – 乳がん画像分析で病理医を上回る識別精度を達成
乳がん超音波検査でAIの可能性を示す新研究
イスラエル Spring Vision社 – 網膜血管マッピング技術を宇宙で展開
2022年予定の民間人宇宙飛行士4名によるISS(国際宇宙ステーション)滞在ミッション「Ax-1」に、イスラエル発のスタートアップ Healthy.ioの腎機能検査AIアプリが組み込まれることを先日紹介した(過去記事)。同ミッションに、イスラエル人のEytan Stibbe氏が宇宙飛行士として約5000万ドルの費用を自己負担して参加することが背景にある。Stibbe氏が宇宙で実施するイスラエル発の研究プロジェクトは、現在44種が計画されているという。
イスラエルのメディアJerusalem Postでは、参加プロジェクトのひとつであるSpring Vision社の網膜撮像技術「iCapture45」について報じている。iCapture45は、異なる波長のLED光を利用して撮像する「光干渉断層撮影(OCT: Optical Coherence Tomography)」の画像に独自アルゴリズムによる解釈を加え、網膜の小血管を自動マッピングすることができる。これを用いた実験が採用された背景には、微小重力環境が視力低下を招く「宇宙飛行関連神経眼症候群(SANS: Spaceflight-Associated Neuro-ocular Syndrome)」の存在がある。過去10年間で全宇宙飛行士の約3分の2がSANSを発症しているとされ、フライトからの帰還後に一部は回復するものの障害が残るケースもある。iCapture45の実験は、宇宙飛行士の目の構造変化を観察し、未解明の部分が残るSANSの発症原因解明などを目的としている。
iCapture45は地球上においても、全身の疾患予測や診断に役立つ可能性を秘めている。Spring Vision社の臨床研究責任者であるEyal Margalit教授は「一般的に重篤な全身疾患は、初期の段階で網膜血管に特徴が反映される傾向がある。そのため目の小血管をマッピングすることに大きな利点がある」と語り、心疾患・糖尿病・腎疾患・神経疾患の警告サインとして技術の応用を計画している。
関連記事:
宇宙進出するイスラエル医療AIスタートアップ「Healthy.io」
網膜から心血管疾患発症を予測するAIシステム
英ニューカッスル大学 – 神経変性疾患を網膜スキャンで検出
米国眼科学会2019より – 糖尿病性網膜症のリアルタイムスクリーニングAI
パンデミック下における「遠隔医療利用の社会格差」
COVID-19のパンデミックに伴い、世界各国において遠隔医療を巡る規制緩和と、当該マーケットにおける新規プレイヤーの急増を認めた。一方、我が国での「遠隔医療への患者アクセスの公平性」についての報告は非常に限られていた。東京大学で公衆衛生学・医療政策学の研究を行う宮脇敦士助教らの研究チームは、遠隔医療利用と社会経済的要因の関係を調査し、Journal of Medical Internet Researchから結果を報告している。
このほど公開された研究論文によると、18~79歳の研究参加者24,526名において、遠隔医療利用は2020年4月段階における2.0%(497名)から、同年8-9月時点で4.7%(1,159名)と倍増していたという。また、一貫して若年における利用が目立ったが、70歳以上の高齢者における利用割合も、対象期間中に増加していた。さらに、4月時点では観察されなかった「最終学歴が大学の者は、高校以下の者と比較してより遠隔医療を利用する傾向」および「都市部在住者は農村部在住者と比較してより遠隔医療を利用する傾向」が、8-9月時点でみられるようになっていたとのこと。
著者らは「COVID-19パンデミックに伴い、若年者だけでなく高齢者における遠隔医療利用の拡大も進み、必ずしも世代間ギャップは大きくなっていない」として、医療ニーズの大きい高齢者での利用が進むことを前向きに捉える。一方、「学歴と居住地に関する利用格差は拡大した」点を強調し、パンデミックに伴う遠隔医療へのアクセス向上が、不均一に浸透している事実を指摘する。これは「遠隔医療の利用拡大が国民の一部を置き去りとしている可能性」を示唆しており、平等なアクセスを達成するための有効な政策的介入の必要性が明らかとなっている。
関連記事:
Amazon Care – 忍び寄る遠隔医療業界の「Xデー」
米シカゴ大学 – 「COVID-19と健康格差」のモデリング計画
健康の人種格差解消の鍵は地域の理髪店に
ニューヨーク大学 – 在宅脳刺激による精神神経疾患の遠隔治療プログラム
遠隔医療を助ける新しい自律型ドローン
網膜画像から近視を識別する深層学習アルゴリズム
2050年までに世界50億人が近視となることが推定され、そのうちの20%は「近視性黄斑変性症」のリスクを伴う強度近視であるという(参照論文)。強度近視は眼底網膜の菲薄化をきたし、裏面から侵入する異常血管の出血によって視力が低下する状態を近視性黄斑変性症と呼ぶ。出血の程度によって失明リスクもあるため、近視の検出と管理は視力予後にとって重要である。
シンガポール国立大学などの研究チームは、網膜画像から近視性黄斑変性症と強度近視を識別する深層学習アルゴリズムを構築した。研究成果はThe Lancet Digital Healthから公開されている。研究チームは22万を超える網膜画像を複数のコホートデータベースから取得し、アルゴリズムのトレーニングと検証を行った。シンガポールのデータによってトレーニングと内部検証を経たアルゴリズムは、中国・台湾・インド・ロシア・英国においてもその妥当性を検証した。このアルゴリズムは、近視性黄斑変性症でAUC 0.969、強度近視で0.913と高い識別精度を示すとともに、眼科専門医6名との比較においても、両疾患の識別においてアルゴリズムは全員のパフォーマンスを有意に上回っていた。
研究チームは「深層学習アルゴリズムが、来たる大量近視時代の有用なスクリーニングツールとなり得る」ことを指摘し、医師の臨床的意思決定を支える主要な臨床サポートツールとしての発展に期待感を示している。
関連記事:
網膜から心血管疾患発症を予測するAIシステム
英ニューカッスル大学 – 神経変性疾患を網膜スキャンで検出
アフターコロナの英国眼科検診はAIスクリーニング「EyeArt」でコスト削減へ
緑内障の遺伝的リスク予測モデルの構築
愛猫の痛みを教えてくれるAIアプリ「Tably」
猫が痛みや不快感を感じているか、他の愛玩動物と比較しても猫の行動から潜在的な痛みの兆候を分析するのは難しいとされる。客観的な痛みの評価が困難であることは、どんなに熱心な飼い主であっても適切な受診や治療の遅れを招きかねない。カナダのスタートアップ Sylvester.AI社は、AI手法で猫が痛みを感じているかを識別するアプリ「Tably」を開発している。
同アプリでは、愛猫の写真を撮ることでそのボディランゲージ指標から痛みを感じているかを識別する。アルゴリズムの中心となるのは、モントリオール大学附属教育動物病院で開発された「Feline Grimace Scale」という指標で、その研究成果は scientific reports誌に報告されている。このスケールでは、5つのマーカー(①耳の位置、②目の開き具合、③鼻先からあごを含む口元を示す通称「マズル」の緊張、④ヒゲの位置、⑤頭の位置)が0-2点でスコアリングされ、猫が潜在的に感じている痛みを評価する。スケール解析のため、Tablyでは猫の画像から機械学習によって構築されたアルゴリズムが使用されているという。
現在Sylvester.AIの公式サイトから、技術に興味を持ったユーザー向けにベータ版が提供されている。これまで飼い主にとって時間がかかったり複雑過ぎた愛猫の痛みの評価に、AI駆動の新たな信頼できるソリューションが確立されるか。全世界の愛猫家と猫たちを強力にサポートするアプリとなるかもしれない。
関連記事:
猫の捕食本能を抑えるAI? – 感染症予防の観点から
獣医学におけるAI技術の可能性
AIによる高齢者の疼痛評価
豪PainChek – 表情分析AIアプリで認知症高齢者の痛みを代弁
痛みを数理モデルで解釈する
AI研究で新たに認識された「学生の自殺リスク予測因子」
COVID-19のパンデミックが精神的な健康に悪影響を及ぼしているとの指摘が相次ぐ中、特に学生の死因の最上位である自殺リスクをどのように推定するべきか。カナダとフランスの研究チームが、学生の自殺行動を正確に予測し得る要因を機械学習アプローチによって特定している。
カナダ・マギル大学のニュースリリースによると、研究は2013年から2019年の間に少なくとも1年間の追跡調査を受けた「フランスの大学生5,000名」あまりのデータから、自殺行動の予測因子を特定したというもの。研究に参加した学生の約17%が、1年間の追跡期間で自殺行動を起こしていた。70の潜在的な予測因子が検討され、最も高い予測力を示したものは、自殺念慮、不安、抑鬱症状、および自尊心で、これら4つによって自殺行動の約80%を検出することができた。研究成果はScientific Reports誌に掲載されている。
研究チームによると「自尊心が自殺行動の予測因子の上位4つに入ることは予想していなかったことであり、大規模データに基づく機械学習アプローチでなければ発見できなかっただろう」と語っている。これまで専門家の間でも認識されにくかった「自尊心」という顕著な予測因子を得たことで、研究と予防の双方で新たな道が開かれることを研究チームは期待している。
関連記事:
「若年成人の自殺企図予測」において機械学習が果たすべき役割
自殺リスクのリアルタイム予測モデルは臨床現場で性能を発揮するか?
Clairity – 音声から自殺リスクを推定するAIアプリ
メンタルヘルスケアにAIを用いるスタートアップ5選
IBM Report – 医療データ侵害の平均コストは920万ドル
IBMが28日明らかにした調査結果によると、ヘルスケアセクターはデータ侵害(データブリーチ)に伴うコストがトップの業界で、実に平均923万ドル(約10.1億円)にも及ぶという。これは2020年の報告から200万ドル増加しており、「新型コロナウイルスのパンデミックによる運用シフト」によってセキュリティインシデントのコストが高くなっていることが考察されている。
レポートによると、2020年にパンデミックへの対応策として60%の組織がクラウドベースのデータ管理に移行した。結果的に急速なテクノロジー導入はセキュリティ対策の最適化を遅らせ、データ侵害に伴うコスト増を来した形となった。医療情報は究極の機微情報であるため、対策単価が高いことは知られてきたが、本報告ではメガブリーチ(5000~6500万件の記録が危機に曝されたケース)の平均コストは4億ドルを超えた。
また、データ侵害の特定と封じ込めに要した時間は平均で287日であり、およそ半数にあたる44%のケースでは医療情報を含む個人情報が公開されていた。一方、AIを含むセキュリティの自動化戦略が大幅なコスト削減につながっている点も指摘されており、自動化を導入していない組織に対してコストの実際値として半分以下となっている事実を認めている。
関連記事:
サイバー攻撃によって50万人の患者情報が流出
英Sensyne Health – 米病院ネットワークとの戦略的研究契約を締結
Truveta – 米国における巨大データプラットフォームを構築
71%のモバイルヘルスアプリに高レベルのセキュリティ脆弱性 – 米 intertrust 2020 レポート
X線データから3D画像を再構築する深層学習技術
米国エネルギー省傘下のアルゴンヌ国立研究所は、X線データを3次元画像として視覚化する新しいフレームワークを開発した。32-CDI-NNと呼ばれるこの新しいフレームワークは、収集データに対して従来よりも大幅に高速な3次元化を実現している。
コヒーレント回折イメージング(CDI)は、超高輝度X線ビームをサンプルに反射させるX線技術で、光線は検出器によってデータとして収集され、画像に変換される。現在の検出器はビームが持つ情報の一部しかキャプチャしていないという限界があり、不足データを埋めるための処理は計算機に依存している。ただし、このプロセスは途方も無い時間を要するケースもあるため、抜本的な解決策が求められてきた。アルゴンヌ国立研究所の研究チームは、不足している情報を考慮せず「オブジェクトと、オブジェクトが生データから直接受ける変化」を認識するようにニューラルネットワークをトレーニングしたという。
3D-CDI-NNの実証試験では、欠落している情報を補うために通常必要とされるよりも少ないデータで画像を再構築できることも確認している。新技術は生物学・医学領域における生体構造に関する3Dイメージング技術を大きく進歩させる可能性を秘める。また、環境に透過するX線により「数ナノメートルのスケール(1ナノメートルは10億分の1メートルに相当)」で材料を観察することができるため、材料科学領域からもコヒーレント回折には熱い視線が注がれている。
研究報告:Rapid 3D nanoscale coherent imaging via physics-aware deep learning
関連記事:
GE Healthcare – MRIから合成CT画像を生成するAIソリューション
眼に触れずに光音響画像を得る新研究
Canonの画像再構成AI技術がPET/CTでFDA認証取得
Zebra Medical Vision レントゲン画像から三次元モデルを構築するAI技術
顔の3D画像から睡眠時無呼吸症候群を識別するAIアルゴリズム
AIツールが患者の健康リテラシーを向上させる可能性
患者が自分自身の医療記録にアクセスする権利は保障されている。しかし、それによって自動的に「内容の理解や適切な健康上の意思決定」ができるようにはなるわけではない。その課題解決のため、医療記録へアクセスする患者の「健康に関するリテラシーを向上させる自然言語処理AIツール」が研究されている。
米ノートルダム大学のニュースリリースによると、同大の研究チームは電子カルテの理解度を確認するツール「ComprehENotes」を開発し、医療用語を患者向けに翻訳し理解を助けるツール「NoteAid」の有効性を検証した。マサチューセッツ州の地域病院から募集された試験参加者はComprehEnotesのテストを受ける際に、NoteAidでテキスト上にマウスカーソルを置くと医療用語の定義が表示されるという介入を受けた。その結果、介入なしの対照グループよりもNoteAid介入群ではComprehENotesテストでの理解度スコアが有意に高かった。研究成果はJournal of Medical Internet Research誌に掲載されている。
同研究は、教育レベルの低い患者を含む地域病院であってもNoteAidが有効であることを示唆する。自然言語処理ツールが患者の健康リテラシーを向上させる証拠を得て、研究チームのJohn Lalor氏は「患者の読解レベルを考慮してツール内の辞書を評価できれば、専門用語として辞書に載せるべきものと、珍しく理解できない用語であっても患者の理解度にとって重要ではないものを取捨選択できるようになる」と語っている。
関連記事:
AI時代に求められるITリテラシー
One Drop – 慢性疾患患者向けのAI健康管理プラットフォーム
AIリテラシーが医療者に欠如?
「AIによる臨床記録再構築」が医師の時間を節約する
医師は患者1人あたりの診療時間の62%をカルテレビューに費やしており、最も時間を要するステップは臨床データの確認であるという。スタンフォード大学の研究チームは、このレビュープロセスを効率化するため、患者情報をAIによって分類・再構築する取り組みを行っている。
JAMA Network Openから23日公開された研究論文によると、同チームが開発したAIシステムの正確性と有効性を確認するため、12名の医師を対象とした前向き研究が行われた。ここでは消化器科専門医らへの紹介患者における臨床記録を、1. 標準的なもの 2. AIによる最適化を受けたもの としてそれぞれ提供し、臨床医に対する22の質問によって各臨床記録からの情報検索時間や満足度などを調査・比較した。結果、標準的な臨床記録のレビューと比較して、AIシステムによる最適化を受けたものは18%の時間短縮を実現し、データ取得の精度にも差はなかった。さらに12名の医師のうち11名は、標準的なものよりもAIによって再構築されたものを好むことも明らかにしており、患者情報の抽出支援にAIが有効である可能性が示唆された。
著者らは「医療データは増え続けており、この事実は臨床医のストレス増大に重大な影響を与えている。AIシステムに対するユーザーの親しみやすさが増すとともに、システム自体がさらに強化されることで、大量の患者記録であっても医師による情報抽出がさらに改善していくことが期待される」と述べている。医療の生産性や質的向上に貢献するばかりでなく、「医師の負担軽減に直接的に寄与するAIシステムを構築し得ること」を示す好例と言えるだろう。
関連記事:
Realyze Intelligence – 電子カルテからハイリスク群を抽出するAIプラットフォーム
EHRコホートを用いた肺がん予後予測
テクノロジーへの不満が医療者の倦怠感を助長する
AIで医療現場はもっと生産的になれる – Googleが医療文書用ツール公開
アスリート用デバイスが巻き起こすテクノロジードーピングの議論
アスリート達のパフォーマンス向上のため、ウェア・靴・コンディショニング・ウェラブルデバイスなどに先端技術が駆使されている。ときにそれらは飛躍的な記録更新に貢献し「テクノロジー・ドーピング(technological doping)」に相当するとみなされて大きな議論を引き起こす。
South China Morning Postでは、東京2020オリンピックにおいてテクノロジーを活用するアスリートの事例が特集されている。特にウェアラブルデバイスは前回オリンピック以降さらに進化を遂げ、選手達の心拍数データや身体の動きをAIによって解析することで、最適なトレーニングやコンディショニングの実現が模索されている。アスリートが市場で合法的に提供されている技術を活用するのは当然の権利であるという意見の一方で、高度なスポーツテクノロジーの利用が、資金力のある国のチームと発展途上国のチームとの不平等を悪化させているという見方もある。
Speedo社の競泳水着やNike社のランニングシューズが驚異的なパフォーマンスを発揮して規制の対象となったように、今後も各種新技術導入に伴うスポーツイノベーションと一定のレギュレーション追加が繰り返されることは疑いようもない。カナダのレジャイナ大学でバイオメトリクス学の教授を務めるJohn Barden氏は「アスリートで検証されたウェアラブル技術が、高齢者の歩行リスクの評価に役立つ将来性を示すなどしており、スポーツ科学の向上が社会に多くの利益をもたらすことを期待している」と語っている。
関連記事:
AIはドーピングを撲滅できるか?
SwRI BIOCAP – マーカーを必要としない3Dモーションキャプチャ
プロアスリート仕様の医療グレード小型ウェアラブル心拍センサー – Sports Data Labs社
マイクロ波ドップラーでNCAAアスリートの動きを評価するAIアルゴリズム