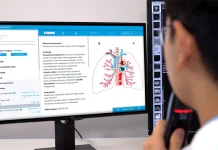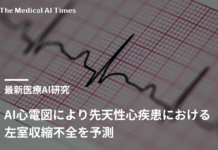医療とAIのニュース 2021
年間アーカイブ 2021
Muse Healthcare – ターミナルケアへのAI活用事例
VNA Health Groupは、ニュージャージー州とオハイオ州に在宅医療・ホスピスなどの地域特化サービスを提供する米国最大級の非営利ヘルスケアプロバイダーである。同グループはMuse Healthcareが提供するAIシステムを全面実装し、あらゆる患者のリスク層別を実現している。
Museのテクノロジーは、臨床評価・投薬状況・バイタルサインなど種々の臨床関連データを取り込みモデル化することで、ホスピス患者のリスクを層別し「追加ケアの必要性」を医療者に警告することができる。VNA Health GroupはMuseのリスク予測モデルに基づき、個別化されたケアプランの作成と経時的な最適化を繰り返すことに成功しているという。
Museによる4日付けニュースリリースでは、VNA Health Groupで研究部門を率いるRobert J. Rosati博士の言葉として「患者が死に近づくほどその医療的ニーズが変化することを我々は実感していた。それらを適切に検出し、プラン変更を促すことのできるアプリケーションとしてMuseのテクノロジーは最適と言える」とする。同施設での実運用では「臨床医からの高い評価」を受けている点にも言及しており、ケアの質的改善をもたらす画期的システムとして現場からの期待も大きい。
関連記事:
AIによる高齢者施設のCOVID-19対策 – カナダ「AiCoV19」プロジェクト
米Careline Health Group – ホスピスケアへのAI利用
社会的孤独をスピーチから解析する研究
Biobeat – リモート患者モニタリングプラットフォームでCEマーク認証を取得
イスラエルのBiobeatは、ウェアラブルデバイスによって「リモートでの非侵襲的患者モニタリングソリューション」を提供する医療AIスタートアップだ。Biobeatはこのほど、同プラットフォームでCEマーク認証を取得したことを明らかにした。
4日、Biobeatが明らかにしたところによると、今回の承認には「手首および胸部のウェアラブルモニタリングデバイス」による血中酸素飽和度・呼吸数・血圧・脈拍・脈圧・心拍出量・皮膚温などの各種バイタルサインのモニタリングが含まれるという。このプラットフォームはクラウドベースのウェブ管理が可能で、患者の病状悪化を事前予測し医療者に警告することもできる。
CEOを務めるArik Ben Ishay氏は「今回の承認により、我々は欧州におけるヘルスケア全体の質的向上と患者転帰の改善という目標を、一層推進することができる」とする。BiobeatのAIソリューションは既に世界数十の医療センターで実臨床利用されており、CEマーク取得に伴う今後の大幅な利用拡大が見込まれている。
関連記事:
スマートスピーカーを利用した心拍モニタリングシステム
呼気でCOVID-19感染検出とワクチン効果のモニタリング
遠隔患者モニタリング: RPMの普及に不足しているものとは?
入院患者の転倒を防ぐAIモニタリングシステム
スタンフォード大学 – 足首の外骨格システムで歩行速度を40%向上
米スタンフォード大学の研究チームは、ランニングシューズに取り付け可能な新しい外骨格デバイスにより、デバイスを利用していない時に比べて平均で42%の歩行速度改善がみられることを明らかにした。特に加齢に伴う歩行機能の低下は、日常生活の質低下とフラストレーションの増大を招く。研究者らは歩行速度を「回復」させるだけでなく、さらなる「向上」を狙うとしており、継続した取り組みを明らかにしている。
このほど、IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineeringから公表されたチームの研究論文によると、この外骨格システムはモーターと独自のAIアルゴリズムにより歩行をサポートするもの。Human-in-the-loop機械学習(人間がアルゴリズム構築の学習・テストの両段階に関与し、絶え間ないフィードバックループを形成する)により、各ユーザー個別の最適設定を実現する。検証研究では10人の健常成人を対象としたが、近く高齢者による同等の歩行テストを行うことも明確にしている。
実際のデバイス写真はスタンフォード大学の公式ページより確認できる。パワードスーツの類型としてイメージするよりは圧倒的に小型軽量で、実運用を考慮した設計が見て取れる。高齢者の自律的活動を支援できる点でも本システムの意義は大きく、需要の規模は計り知れないだろう。
関連記事:
AIとコンピュータビジョンによる自律歩行型外骨格
リハへのAI活用 – 脳卒中患者における下肢装具の必要性を予測
高齢者サポートAIの「MyndYou」400万ドルの追加資金を調達
Canon – 画像再構成ディープラーニング技術「AiCE」の米FDA承認拡大
ディープラーニングによる画像再構成技術(DLR: Deep Learning Reconstruction)は、AI技術の隆盛によりCTやMRIで実用化が進み、より低線量・短時間で高精細な画像が得られるようになった。Canon MedicalのDLR技術「AiCE: Advanced intelligent Clear-IQ Engine」については以前にも紹介した(過去記事)。
Canon Medical Systems USAの26日付プレスリリースによると、同社MRIのAiCE技術において、これまで米FDAで認められていた「脳と膝」の適応領域から、「前立腺・全関節・心臓・骨盤・腹部・脊椎」といったほぼ全身の領域(96%)にDLRの適応拡大が承認されたことを発表した。
今回の米FDA承認拡大を受け同社では、「AiCE適応の1.5テスラ」 vs 「非適応の3テスラ」で違いを判別できるか挑戦する「AiCE Challenge」をバージョンアップし公開している。隣り合う組織同士の境界の精細さを判断基準とすることで、筆者の場合には得意な臓器では正解したが、正答根拠は正直なところ明確には示しにくいほどだった。もし高度に盲検された場合には差の認識は困難かもしれない。脳と膝で公開されていた過去のAiCE Challengeとあわせて是非体感してみて欲しい。
関連記事:
CanonのAIがFDA承認- CTの放射線被曝を低減しながら超高解像度画像を再構成
キヤノンメディカルシステムズUSA – Zebra Medical Visionと提携しAI画像診断を提供
画像検査用AIが誤診を生む?...
Forbes AI 50 – 2021年注目すべきAI企業トップ50
Forbesは26日、「2021年 注目すべきAI企業トップ50」を公開した。これは同社がSequoia CapitalおよびMeritech Capitalと協力して行うもので、2021年版で3回目となる。事業の中核にAI開発を据える米国企業を取り扱い、リスト入りを希望する企業からは詳細情報(技術・ビジネスモデル・顧客・資金調達・収益状況など)を取得し、アルゴリズムによる定量評価によってランク付けしている。なお、主要なテクノロジー企業などによって買収された、あるいは大規模な資金提供を受けたAI企業は検討せず、個人所有の民間スタートアップを対象としている。
フルリストはこちらから参照できるが、ヘルスケア領域については下記の9社がリスト入りしていた。その一部は本メディアにおける過去記事でも取り扱いがあるので、あわせて参照のこと。
Atomwise:AIアプローチによる治療薬候補の特定(過去記事)
Ezra:MRIスキャンから悪性腫瘍を検出するAIシステム
Genesis Therapeutics:ニューラルネットワークと生物物理シミュレーションによる新薬開発
Intelligencia:臨床試験の成功可能性やその改善方法に洞察を与えるAIシステム
Komodo Health:臨床試験から臨床現場までをつなぐ医療データ分析プラットフォーム
Nines:頭部・胸部など多部位、多モダリティでの画像スクリーニングAI
Verge Genomics:AIとゲノムデータによる神経変性疾患の新薬開発
Viz.ai:頭部CT画像での梗塞・出血病変の識別AI(過去記事)
Whisper:音声をノイズから分離することで難聴者をサポートするAIワイヤレスデバイス
GetSkinHelp – モバイルAIアプリでカナダの皮膚科受診を変革
新型コロナウイルスによる制約から、日常的な疾患で医療機関にかかることの困難さが注目された。カナダでは、皮膚科受診のあり方を変えるAIモバイルアプリ「GetSkinHelp」が2021年5月下旬から無償提供開始される。開発元のSkinopathy Inc.はデジタルヘルスでの革命を志し、2020年にカナダで創立されたスタートアップだ。
GlobeNewswireでのプレスリリースによると同アプリのAIは、撮影した皮膚画像から各種皮膚疾患(皮膚線維腫・血管性病変・基底細胞がん・扁平上皮がん・メラノーマ・異形成母斑・角化症・色素性母斑)を精度88%で判別可能と謳っている。アプリ上で皮膚疾患の可能性をスクリーニングしたのち、数時間から数日以内で専門家とのバーチャルアポイントメントが予約できる。バーチャルアポイントメントを経て、実際の来院や検査・生検といった次のステップを決定する。
アプリのサービスはカナダ各州の医療保険制度に完全に組み込まれているため、利用にあたってユーザーの自己負担は生じない。モバイルで迅速かつ信頼性の高い皮膚疾患管理アプリを提供することで、遠隔地など医療が行き届きにくい地域の人、あるいは通院が困難な人など、カナダの人々にとって有益なサービスとなることが期待されている。
Beyond Next Ventures – 国内最大級アクセラレーションプログラム「BRAVE」が見据えるもの
Beyond Next Ventures株式会社(代表取締役 伊藤毅)は、ベンチャーキャピタルとしての、日本および海外におけるディープテック系スタートアップへの投資にとどまらず、技術シーズの事業化支援や研究領域における経営人材輩出支援、シェア型ウェットラボ・コワーキングスペースといったインフラの提供など、多面的な取り組みによって事業開発を巡る「エコシステムビルダー」となっている。同社が展開する事業開発支援プラットフォームの1つである「BRAVE 」は、国内最大級のアクセラレーションプログラムであり、数多くの有為な技術を形とし社会に実装してきた。
今回はBeyond Next Ventures株式会社の金丸将宏氏に、アクセラレーションプログラム・BRAVEについてをお伺いした。
- この度はお時間を頂き、まことにありがとうございます。まずは自己紹介をお願いします。
Beyond Next Venturesで、アクセラプログラム「BRAVE」を担当している金丸と申します。並行してスタートアップへの投資業務も行っており、AIやメディカル領域を中心に担当しています。
- 早速ですが、本プログラムの概要を教えて頂けますか?
BRAVEは2016年から毎年1回程度開催している、技術系スタートアップの創業期を支援するプログラムです。2ヶ月間のプログラム期間で、技術系スタートアップの課題である、創業メンバーの組成・チーム強化、専門家とのネットワーク、資金調達が可能な事業プランの作成、にフォーカスしたプログラムです。これまで100を超えるチームが卒業し、120億円以上の資金調達を実現しました。
- BRAVEをスタートしたきっかけを教えてください。
技術系スタートアップへの出資支援を行う中で、そもそも会社設立の前段階でつまずいていることが分かりました。具体的には、経営者不在、事業モデルの構築失敗、そしてスタートアップというものの基礎的理解不足、など様々な課題があります。当時でもいくつかアクセレーションプログラムはありましたが、技術系スタートアップの創業支援という意味では十分ではないと思い、ベンチャーキャピタルでありながら、技術系スタートアップの支援に特化したBRAVEを自らつくりあげることを決めました。
- ホームページ上に「6回の開催を経て大幅アップデート」とありますが、今回どのような新しい特徴があるのでしょうか?
大きくは「領域フォーカス」と「支援メニューの強化」です。これまで幅広い領域のシーズを募集しておりましたが、今回からはAI・デジタルヘルス・バイオ創薬・アグリフードにフォーカスして募集しています。それに伴い、より専門性の高いメンターの参画、知財、法務、IT支援など採択チームに広くご活用いただける支援メニューにバージョンアップしました。
- 数あるアクセラレーションプログラムと比較して、本プログラムの強みはどのような点ですか?
アクセレーションプログラムは年々増えており、スタートアップの皆様はどれに参加したら良いのか、違いが分かりにくくなっていると思います。その中でBRAVEは、サイエンス/テクノロジー、創業期の支援に注力していることが特徴です。サイエンス、テクノロジー領域は研究開発が先行するため、プロダクト上市までに時間・資金を要しリスクが高いこと、そして事業計画に高度な専門性が必要であることが特徴です。そのようなスタートアップの支援を行うために、経営人材のご紹介や専門的メンター、そして本領域で投資経験の豊富なキャピタリストが一緒になり事業化支援を行うのがBRAVEです。
- BRAVEのターゲットは主に誰なのでしょうか?
高度な技術シーズを持つ研究チームや技術系スタートアップです。これまで100以上のチームやスタートアップさんにBRAVEにご参画いただいておりますが、およそ4割が起業済、6割が起業前といった印象です。
- 求める参加者像についてはいかがでしょうか?
「事業化や社会実装に強い情熱を持つ方」に、年齢を問わずぜひ参加していただきたいです。会社はどうやって作ればよいのか、どんなフェーズになったら作れるのか、資本政策って?などの起業ノウハウもメンター陣や弊社メンバーで支援させていただきますので、参加者の方には「事業化への情熱」をぜひ持っていただきたいです。
- 本プログラムでの「メンター」は、具体的にどのような役割を担うものでしょうか?
いくつか役割がありますが、専門知識の提供、ディスカッションのファシリテーション、リーダーシップの醸成、などスタートアップに必要な支援をさせていただきます。メンターの方々は、専門家だけでなく実際のスタートアップ経営者、マネジメント経験者などリアルな経験のある方にも参加していただいています。
- 本プログラム参加後の展開として、モデルケースとなるようなスタートアップがあればご紹介ください。
種々ありますが、慶應義塾大学発ベンチャーのConnect社がBRAVE卒業後順調に事業化を進めています。2017年にBRAVEに参加いただいた時は、会社設立前の段階でした。プログラム期間中に経営人材の皆さんと事業プランを作成し、最終ピッチ大会では見事最優秀賞を獲得されました。BRAVE卒業後、無事に会社を設立され、資金調達を行ってガンガン事業化を進めています。我々も出資をさせていただきました。
- パートナー企業側から、本プログラムに対する期待や反響はどのようなものがありますか?
パートナー企業様には「スタートアップとの連携の機会」を一番期待されて参画いただいております。ただ、参加したあとにフィードバックを受ける中で「社内での0→1の参考になった」「ぜひチームに自社のメンバーを参加させていただきスタートアップの立ち上げについて学ばせて欲しい」といったニーズもあることが分かり、教育的側面でもBRAVEをご活用いただいています。
さらに、企業からのカーブアウトのニーズもあることが分かってきました。社内の研究開発プロジェクトを様々な事情で社内で事業化することが難しい場合があり、それを新たなスタートアップとして社外で事業化するケースです。そのようなケースでも、通常のスタートアップと同じように、事業化ステップ・チーム組成・資金調達などが課題となることが多く、そのような社内プロジェクトからBRAVEに参加いただく取り組みも始めました。そこから実際にスタートアップとして事業化しているケースもあります。
- 最後に、プログラム参加を考える方々およびThe Medical AI Timesの読者に対してメッセージを頂けると幸いです。
The Medical...
メイヨークリニックとNASAの協調 – 臨床データから因果関係を明らかにするAIプラットフォーム
米メイヨークリニックの研究チームは、複雑な生物医学データに組み込まれた因果関係を明らかにするAIプラットフォームを開発した。Nicholas Chia博士らの研究チームは、米航空宇宙局(NASA)フロンティア開発ラボのデータサイエンティストや機械学習エンジニアと共同し、このCRISPと呼ばれる新しいフレームワークの検証を行っている。
メイヨークリニックが24日明らかにしたところによると、CRISPは「利用可能な全てのオミックス情報および臨床データを活用することにより、疾患の隠れた原因を明らかにし、疾患予防および治療に向けた新しいターゲットとメカニズムを特定できる」としている。CRISPは、眼前にあるデータを任意に組み合わせ、無数の再現可能な因果推論実験を行うことができる。フレームワークは個々のアルゴリズムにデータを掘り下げ、点と点をつなぎ、原因と結果を説明できるようになる。最終的な出力モデルは各アルゴリズムからの説明を組み合わせることで、臨床医に一連の予測される因果的特徴を提供するという。
研究チームはNASAとの協力により、大腸がんコホートを用いたCRISPの検証によって、大腸がんサブタイプの特定とCRISPの因果推論モデルが機能することを実証したとしている。両者はCRISPをさらに高精度化・高機能化することを目指す。Chia博士は「NASAは次の10年で宇宙飛行士を火星に連れていきたいと考えている。彼らは疾患の原因を深く理解するインセンティブを持っており、私たちは彼らと協力することによって知識の進歩をみている」と語る。
関連記事:
多発性硬化症とベイジアンネットワーク
オハイオ州立大学 – 既存薬に新しい利用用途を見出す深層学習フレームワーク
敵対的生成ネットワークによるアルツハイマー病識別パフォーマンスの強化
PROFID – AIで心臓突然死リスクと植込み型除細動器の適応を検証
心臓突然死は欧州で全死亡の約20%を占め、今なお公衆衛生上の課題となっている。心臓突然死を防ぐ手段のひとつとして、植込み型除細動器(ICD: implantable cardioverter defibrillator)が装着される。従来基準によると、心筋梗塞後の患者で「左室駆出率(EF)35%以下」にICD植込みが推奨されている。しかし、実際にICDで救命できている患者は少数で、EFが35%より高く維持された患者でも心臓突然死の発生が問題となるため、心臓突然死リスクとICD適応を予測する新たなアプローチが待望されていた。
4月23~25日に欧州不整脈学会(EHRA: European Heart Rhythm Association)の2021年次総会が開催され、同学会のプレスリリースでは、ICD適応患者をAI利用で適切に選択するプロジェクト「PROFID」の概要発表を伝えている。PROFIDでは、心筋梗塞患者数十万人を対象とした合計23のデータベースにAI手法を組み合わせ、心臓突然死の個別リスクを示す予測モデルを作成している。そして3,900名以上の患者が参加する2つの臨床試験で新時代のICD治療戦略が検証される。「PROFID-Reduced」では、EF35%以下だが低リスクと予測された患者で、ICD装着/非装着が無作為割り付けされる。「PROFID-Preserved」では、EF35%以上だが高リスクと予測された患者でICD装着/非装着が振り分けられる。
主任研究員のNikolaos Dagres氏は「プロジェクトの目標は、ICD治療の意志決定方法を変え、必要な人にはICDを与え、不要な人にはICDを与えないようにすることです。倫理面・患者視点・医療経済への影響の検証もこの試験と並行します」と述べている。
大腸がん免疫染色から分子標的薬の効果を予測するAI研究
英国では4月にBowel Cancer Awareness Month(腸管がん啓発月間)が展開されている。そこにタイムリーな発表のひとつとして、英リーズ大学から「進行性大腸がん患者の一部に存在するタンパク質を免疫染色標本からAIで解析して分子標的薬の効果を予測する」研究成果が公表された。
リーズ大学の22日付ニュースリリースでは、同大学のグループから学術誌 American Association for Cancer Researchに発表された研究を紹介している。研究内では、転移性大腸がん患者から採取された腫瘍組織に対して免疫染色を行い、染色された腫瘍細胞の割合を機械学習手法で算出し、細胞増殖に関わるタンパク質「アンフィレグリン(AREG)」と「エピレグリン(EREG)」の発現を定量評価した。それら患者へ化学療法としてイリノテカンを投与する際に、分子標的薬「パニツムマブ(商品名: ベクティビックス)」の併用群/非併用群に割り付けて治療効果を検討した。結果として、前述のタンパク質が高度に発現していた患者では、パニツムマブ併用により無増悪生存期間(PFS)が有意に改善したことを確認できた。
「免疫染色の評価に機械学習手法を導入することで、検査法がより実用的となり日常診療において利用が可能となる」と著者らは指摘する。AIによる解析で、病理標本からタンパク質の発現量を治療効果予測のバイオマーカーに用いるのはひとつのトレンドとなってきた。複雑化するがん治療および分子標的薬の選択基準として、今後さらに一般的となっていくAI応用であろう。
関連記事:
Medtronic – 大腸ポリープ検出AI「GI Genius」の臨床試験
PathoFusion – 豪州発の自律型病理診断AIフレームワーク
東京工科大学 – がん幹細胞を識別するAI技術を開発
マウントサイナイ医科大学 – 博士課程にヘルスケアAIコースを新設
米ニューヨーク州マンハッタンに所在するマウントサイナイ医科大学はこのほど、博士課程における医療AIコースを新設することを明らかにした。医学におけるAIと新興技術にフォーカスする同コースは、生物医科学専攻の一部として設置される。今夏から学生の募集が開始され、一期生は2022年秋の入学を目指すこととなる。
マウントサイナイ医科大学が明らかにしたところによると、本コースでは創薬領域をはじめとして、新たな医療AIツールの開発および実装を手掛けていくという。マウントサイナイヘルスシステムが各臨床分門や研究所全体で取得した大規模データ群を利用し、研究開発を加速度的に推進する。
同大学で医療AI領域を主導するThomas J. Fuchs博士は「将来の生物医学系研究者は、増大する医学の複雑さに適応するため相応のスキルセットを身につける必要がある」と述べ、情報システムの使用に関する基礎教育だけではなく、統計学・確率論の背景知識、機械学習ツールを活用したモデル開発と解釈などを学ぶ重要性を強調している。
関連記事:
VRで医学教育を拡張 – 英 Oxford Medical Simulation社
医学生の基礎教育にAI科目導入の必要性
【立教大学大学院人工知能科学研究科・公式インタビュー 】 傑出したAI人材輩出の拠点へ
熟練医が持つ「違和感」のモデル化 – 正常/異常のみのMRIスクリーニングシステム
放射線科医はその読影作業において、限られた時間のなかで緩急をつけた画像診断を行う。一見して「何かがおかしそうなもの」には時間を多く割く。一方で、自身の経験と高度専門知識に基づき、違和感を感じない画像は定式的な確認のみで済ませる。これはある意味で職人感覚に類するものだが、このような熟練医が抱くことのできる適切な「違和感」をモデル化する深層学習アルゴリズムが構築された。
権威ある学術団体「北米放射線学会(RSNA)」が21日公表したところによると、マサチューセッツ総合病院(MGH)やハーバード大学などの研究チームは、複数施設から収集された9,000を超える頭部MRI画像によって当該アルゴリズムをトレーニングしたという。畳み込みニューラルネットワークモデルはあえて「正常/異常」のみを識別するよう設計され、特定の候補診断名を挙げることはしない。これによってモデルのターンアラウンドタイムを大幅に改善するとともに、本来関心があるもの以外の所見を偶発的に捉える機会を逃さない(転倒に伴う脳損傷をチェックした際にも、脳腫瘍の存在を見逃さないなど)。また、このようにシンプルなアルゴリズムは放射線科医による画像読影への強力な支えとなる可能性もある。
同21日にRadiology: Artificial Intelligenceから公開されたチームの研究論文では、比較的良好なモデルパフォーマンスを示しているが、あくまで現時点では予備的研究成果と位置付け、さらなる精度向上と汎化性能の検証を続けるとしている。正常/異常のみを識別するアルゴリズムは興味深い視点であるが、所見に病的意義のないものも多く、異常の閾値をどこに設定するかによっては臨床フローを著しく阻害する可能性もある。「異常」に対しては臨床的重要度を付与して示すなどを考慮することが、臨床現場に受け入れられやすいスクリーニングシステムとしての発展の方向性かもしれない。
関連記事:
乳がん識別AI – 人の学習過程を模倣したAIが放射線科医のパフォーマンスを凌駕
胸部CT画像のAI定量評価で患者転機を予測
MRI画像から腎容積を自動計算するCNNモデル
小児脳腫瘍をMRIから分類するAI研究 – 英ウォーリック大学
米国放射線科医の約30%がAIを使用 – 2020年ACR調査
医療用画像処理におけるAIの市場は、今後10年で10倍以上の成長を見込むとも言われている。画像用AIは現在まで80種以上が米FDAの臨床利用許可を得た。米国放射線医会(ACR: American College of Radiology)は会員を対象としたAI使用に関する年次調査を2020年に初めて実施し、その結果を発表した。
学会誌 Journal of the American College of Radiologyでの年次調査結果発表では、調査に回答した1,861名のうち493名(33.5%)が臨床現場でAIを使用していた。放射線科医のAI使用には、施設の規模が大きく影響しており、大規模施設(施設あたりの放射線科医の人数が多い)ほどAIを使用している傾向がみられた。また、AI利用者の約半数(52.0%)は、診断解釈(Interpretation)の向上目的での使用であった。AIの利用領域で多いものは、頭蓋内出血、肺塞栓、マンモグラフィ(乳がん)で、AIを利用していない施設の約20%が1~5年以内でのAIツール導入を検討していた。
著者らは、今回の調査結果から放射線科の臨床現場におけるAI普及率が想定より緩やかであると結論づけている。調査内でAIを使用していない回答者の理由については、大多数(80%)が「メリットがない」というもので、約3分の1(31%)が「費用を正当化できない」または「AI購入の決定権がない」と答えている。また、AI利用者のほとんど(94.3%)が「パフォーマンスの一貫性のなさ(バイアスなど)」を指摘している。その他に「潜在的な生産性低下」や「診療報酬の不足」への懸念も根強かった。一方で、AIに対する信頼感の低さとは対照的に、使用経験における満足感は高く、AIの価値を実感している結果も見られているため、学会ではAIの導入障壁を今後の課題としている。
関連記事:
NVIDIA 米国放射線医会と提携へ
欧米放射線医学会 AI利用の倫理ガイドライン策定を求める共同声明を発表
リハへのAI活用 – 脳卒中患者における下肢装具の必要性を予測
脳卒中に伴う片麻痺への装具療法は、歩行の改善に明確な効果がある。下肢装具のうち、特に短下肢装具(AFO)は下腿部から足底までを覆う構造を取り、足関節の動きを制限することで効果発現を期待するものだ。韓国・嶺南大学の研究チームは、脳卒中発症後早期での「後にAFOが必要となる可能性を予測する機械学習モデル」を構築した。
チームが19日、Scientific Reportsから公表した研究論文によると、474名の脳卒中患者における臨床データを利用し、この機械学習モデルを導いたという。6ヶ月後の歩行におけるAFOの必要性は足首背屈筋のMRCスコアに従って分類しており、スコア3未満の患者は必要あり、3以上で必要なしとしている。研究チームは、患者がリハビリテーションユニットに移されるタイミング(発症後平均16.2日)での臨床データ(年齢・性別・脳卒中種別・運動誘発電位データ・Brunnstrom分類など)から、このMRCスコア低値を予測するモデルを構築した。結果、ディープニューラルネットワークでAUC 0.887、ランダムフォレストとロジスティック回帰でそれぞれ0.855と0.845と、各モデルは比較的高精度な予測能を示していた。
研究チームは「機械学習アルゴリズム、特にディープニューラルネットワークが回復期脳卒中患者におけるAFOの必要性予測に役立つことを示した」とし、成果の重要性を強調している。リハビリテーション領域におけるAI活用研究は近年増加傾向にある。近傍研究で先行の乏しいものとしては、種々ある下肢装具のうち、患者背景および臨床データからどの装具を選択することで機能予後が良好となるか、臨床的意思決定を支援するAIモデルの構築などが考えられる。個別最適化装具をデータドリブンに設計することも、高齢化の進展に伴う需要の増大が見込まれるため、興味深いシーズとなり得るだろう。
関連記事:
入院患者の転倒を防ぐAIモニタリングシステム
脳卒中発症後における受診の遅れを予測する機械学習アルゴリズム
Viz.aiの脳卒中における「時間」への挑戦
脳卒中の迅速診断をスマホ動画で行うAI研究
SNS上でのCOVID-19陰謀論の進化を追跡するAI研究
COVID-19に関する荒唐無稽な「陰謀論」がSNSによって発信・拡散されることは、公衆衛生上の大きな問題がある。米ロスアラモス国立研究所のグループによって、「SNS上でのCOVID-19陰謀論の進化を追跡するAI研究」が発表されている。
ロスアラモス国立研究所のニュースリリースでは、学術誌 Journal of Medical Internet Researchに発表された「4つの代表的なCOVID-19陰謀論をTwitterから解析する機械学習モデル」が紹介されている。その4つの陰謀論は、「5G電波塔がウイルスを拡散させた」「ビル&メリンダ・ゲイツ財団がCOVID-19を設計または何らかの悪意を持っている」「ウイルスはバイオエンジニアリングまたは実験室で開発された」「COVID-19ワクチンはまだ開発中の危険なものである」といったものである。同研究では2020年1月から5月までのCOVID-19関連ツイート1.2億件から180万件までフィルタリングし、そこからランダムフォレストによる機械学習モデルで上記4種の陰謀論ツイートを特定した。それらを分析したところ、ツイートは否定的な感情を多く含んでおり、陰謀論は時間の経過とともに進化し、無関係な陰謀論あるいは現実の出来事の詳細部分を取り込んでいくことが示された。
陰謀論に取り込まれた現実の一例として、ビル・ゲイツ氏が資金提供した「予防接種記録に使えるという注射可能なインクの開発研究」があった。その話題が2020年3月に紹介された直後から、人口管理のため、COVID-19ワクチンを密かにマイクロチップ的に利用している、といった反ワクチン陰謀論の単語が見られ始めたという。論文の筆頭著者であるShelley氏は「公衆衛生担当者にとって、事実に基づいた広報活動で陰謀論に対抗する手段を戦略的に考えるため、陰謀論がどのように進化し支持を得ているか知ることが重要となります」と語っている。
Hyfe – 咳のトラッキングでデジタルヘルスの未来を開拓
咳は病気の症状として重要で、含まれている医学的な情報は多岐にわたる。咳の情報に焦点をあて、音響疫学(acoustic epidemiology)という新たな分野を開拓し、咳のデータを収集・解析するAIプラットフォームを提供する「Hyfe」という企業がある。
Business Leaderには、HyfeのCEOであるJoe Brew氏のインタビューが掲載されている。同社は一般ユーザー向けに咳をトラッキングするスマホアプリ「Hyfe Cough Tracker」をApp StoreとGoogle Playで提供している。一方、研究者向けにはHyfe Researchというアプリと、Hyfe Screeningというウェブサイトを提供し、そこで研究に必要なデータセットを共有する。スマホアプリ上では、爆発的で短い突然の音のピークを検出し、ユーザーのプライバシー保護と通信帯域幅の節約目的から、0.5秒以下のピーク音のみを記録していく。サーバー上へ安全に送信されたデータは、機械学習モデルで、咳、くしゃみ、その他の音のように分類され、そこから疾患別の分類など下流のアルゴリズムが実行される(疾患分類モデルは現在未公開)。
現在、一般ユーザーが体験できるのは咳の頻度の数値化、いわゆる「Fitbitスタイル」で咳の回数や時系列をダッシュボードに載せ、咳の音声データ再生や、データを医師や友人と共有することである。Brew氏は「自身の咳の量を正確に把握している人はいない」として、まずはこの情報だけでも健康管理に役立つことを強調する。研究者向けにはデータ集計・分析の専用ダッシュボードが用意され、研究への活用例は無数にあると同氏は期待している。
Hyfe社の立ち上げと事業の加速にはCOVID-19のパンデミックが背景にあり、将来的には新興感染症アウトブレイクにおける初期段階の検出や、結核のパンデミック監視などでの利用も想定している。Brew氏は「洗練された最先端のテクノロジーがSNSのクリック率を高めている一方で、ヘルスケアのインターフェースがいまだに紙とペンのようなプロセスに頼っている事実を憂いてきた」と、Hyfeのアイデアを生んだ思いを語っている。
関連記事:
周囲の咳の音から感染症アウトブレイクを監視 – ポータブルAIデバイス FluSense
咳を出させて無症状のCOVID-19感染患者を識別するAI – MITが発表
造血幹細胞移植のレシピエントにおける「敗血症発生」を予測する機械学習モデル
造血幹細胞移植におけるレシピエントでは、複合的要因によって免疫不全状態となるため、あらゆる感染症リスクを伴う。なかでも、感染症に伴って深刻な臓器障害に至る敗血症は、罹患後の治療成績も決して良好ではないことから発生リスクの高精度な予測手段が求められてきた。米ワシントン大学の研究チームは、種々の臨床データから「造血幹細胞移植レシピエントにおける敗血症発生」を予測する機械学習モデルを開発している。
JAMA Network Openから19日公開されたチームの研究論文によると、2010年から2019年にかけて、ワシントン州シアトルのフレッドハッチンソンがん研究センターで施行された1,943名の移植データに基づき、この予測モデルは構築されたという。移植例のうち、実に1,594名に少なくとも一度の菌血症を認めた。全菌血症エピソード8,131のうち、238(2.9%)については敗血症が疑われるものであった。チームが開発した予測モデルはAUC 0.85を示し、既存ツールで最も高精度な予測を示したもの(AUC 0.64)に対して大幅な精度向上を実現している。
研究チームは「新しい機械学習モデルは既存ツールと比較して、敗血症リスクの高い菌血症推定および短期死亡のいずれについても優れた予測精度を持つ」ことを強調し、臨床現場におけるタイムリーな敗血症リスクの検出システムとして利用できる可能性を指摘している。
関連記事:
初期CT画像から急性呼吸窮迫症候群の発症を予測する機械学習モデル
血算から妊産婦の菌血症を予測する機械学習アルゴリズム
メイヨークリニック – AIと患者データを結ぶ新規プラットフォームを発表
日常的に取得される臨床データを解析し有用な知見を導くことは、長らくヘルスケアにおける難題であり希望でもあった。機械学習をベースとするデータサイエンスにおける技術革新は、臨床ビッグデータの有効活用をまさに実現しようとしている。米メイヨークリニックはこのほど、新しいmHealthツールとして「Remote Diagtostic and Management Platform(RDMP)」を発表した。
メイヨークリニックによる公表によると、この新しいプラットフォームでは各種患者デバイスをAIリソースに接続し、医療者による診断など、重要な臨床的意思決定支援を実現するものだという。メイヨークリニックで循環器分野を率いるPaul Friedman医師は「重要なことは症状が現れる前に疾患を検出し、これらイベントの発生を防ぐことだ」とし、例えば心電図など、医療ワークフローに既に統合されている「ユビキタスで安価なポイントオブケア検査」にAIを加えることの重要性を強調する。
メイヨークリニックはこの新規プラットフォームを支え、広域展開を実現するため、新たに2つのデータ解析企業を設立している。クラス最高のアルゴリズムとケアプロトコルの提供を目指し、医療界の巨人は確かな歩みを続けている。
関連記事:
Google – ミネソタ州の新拠点でメイヨークリニックとの連携を強化
その息切れは心不全かCOVID-19か? – 米メイヨークリニックのAI拡張心電図
イノベーションと患者情報の保護 – メイヨークリニックの事例
Perimeter – AI搭載OCTシステムでFDAのBreakthrough Device Designationを取得
がん組織断端の評価などを目的として、高い空間分解能で視覚化する光干渉断層撮影(OCT: Optical Coherence Tomography)システムを開発するPerimeter Medical Imaging社の、FDA 510(k)認証について先日紹介した(過去記事)。
Business Wire掲載のニュースリリースによると、PerimeterはOCTとAIを組み合わせた同社製品が、FDAの「Breakthrough Device」に指定されたことを発表している。このプログラムへの指定によって今後、製品開発中のやり取りが加速され、当局への提出物の審査などが優先される。
Perimeter社の共同創設者であるLiz Munro氏は「当社のAI搭載OCTシステムが、摘出した乳がんの術中断端評価において、既存の機器に比べた大きなメリットの可能性を評価され、Breakthrough Device Designationを取得したことを嬉しく思います。FDAの審査チームとの生産的なやりとりとタイムリーな審査に感謝し、臨床検証の最終段階でFDAと協力していくことを楽しみにしています」と述べている。
関連記事:
Perimeter – 術中に病変微細構造を確認できるOCTシステムでFDA認証を取得
乳がんの取り残しを防ぐAI技術 – Perimeter Medical Imaging
新時代の時計描画テストがアルツハイマー病を早期検出
認知機能スクリーニングにおいて、時計描画テスト(CDT)は簡便かつ有用な手法として50年以上に渡って臨床現場で活用されてきた。米Linus Healthが提供するDCTclockは、CDTの単なるデジタル版ではなく、時計描画のプロセスさえも評価に加えることで、早期アルツハイマー病における微弱な変化を捉えることに成功している。
Linus Healthが14日明らかにしたところによると、米マサチューセッツ総合病院(MGH)が主導した臨床研究では、このデジタル版CDTの結果はアミロイド斑の有無と有意な相関を示すことを明らかにしている(研究論文)。実際、無症候である早期アルツハイマー病の検出に一定の効果を示しており、古典的試験への技術革新が新たな臨床ツールを生み出した形だ。DCTclockは、米食品医薬品局(FDA)におけるクラスⅡ医療機器の認証を既に受けている。
通常のCDTは描き上がりを評価するものだが、DCTclockはタスクプロセス全体をキャプチャし、AIによって手先の動きや空間パターン、描画特性などを分析することで認知機能障害における微弱な変化を検出することができる。
関連記事:
認知症を持つ人々のためにテクノロジーができること
アルツハイマー病に既存薬再利用を促進するAI研究
眼球運動の様子から理解力を予測する機械学習モデル
全ゲノムシーケンス分析 – 13の新しいアルツハイマー病遺伝子が明らかに
血清ラマン分光法とAI – アルツハイマー病の新しいスクリーニング手法開発に向けて
敵対的生成ネットワークによるアルツハイマー病識別パフォーマンスの強化
COVID-19感染検知アプリëlarmがニュージーランド国境警備隊で試用
COVID-19による自覚症状の数日前に早期の体調変化をとらえ警告を発するアプリ「ëlarm」を以前に紹介した(過去記事)。開発元のDatamine社はニュージーランドを拠点とした企業である。同アプリは、ニュージーランド国境警備隊員を対象とした最大500名の試用を5月上旬まで実施することが発表されている。
ニュージーランド政府の情報サイト Unite against COVID-19のリリースによると、同国保健省によってëlarmの1ヶ月間トライアルが国境警備隊員のボランティアを対象として実施されている。アプリをインストールするFitbitやApple watchのようなスマートウォッチを持たない国境警備隊員には、Datamine社からウェアラブルデバイスが提供される。
ニュージーランドは人口約500万人に対してCOVID-19の累積死亡者が26名と、封じ込めに成功している国のひとつとされる。現状、同国内でCOVID-19感染リスクが最も高い職種のひとつは、水際対策として国境で働く人々といえる。個人向けの月額制・サブスクリプションで提供されているëlarmについて、私企業が従業員へ導入したケースはみられていた。一方、政府によるウイルス対策の前線での試用は初めてということで、大きな話題となっている。
余談だが、The Medical AI Times編集部でëlarmを試用した続報として、1度だけ「Slightly Elevated」と警告が発せられた。それはアルコール摂取翌日に強い脱水症状での心拍数変化を捉えたようで、その後も編集部員で何らかの感染は確認されていない。
関連記事:
ëlarm – COVID-19発症前の感染疑いを警告するウェアラブルAIアプリ
中皮腫のCT診断AI – Canon Medicalとグラスゴー大学
建材などに使用されてきたアスベスト(石綿)関連の健康被害として、肺の悪性腫瘍である「中皮腫」がある。スコットランドでは、英国の主要産業として造船・建設でアスベストが多く使用されてきた経緯から、国際的にも中皮腫の発生率が高い地域として知られる。そのスコットランドを拠点としたCanon Medical Research Europeとグラスゴー大学は、中皮腫のCT診断に焦点を当てたAIツールを開発している。
グラスゴー大学のリリースによると、中皮腫のCT診断AIは腫瘍専門医の教師データから学習し、病変の検出と測定を正確に行う。同ツールは、がんに対するイノベーション技術に資金提供するスコットランド内のプログラム「Cancer Innovation Challenge」の一環で開発され、検証結果の発表を予定している。中皮腫は、一般的な腫瘍のように球体ではなく、組織表面上で「皮」のように複雑な成長をみせるため、CTでの診断が難しいがんの1つとされる。また、中皮腫の治療法は限定的で、今後の新規臨床試験も不可欠であるため、AIによる腫瘍検出・測定の効率化および自動化は臨床試験をより低コスト・短時間・高精度にする可能性も期待されている。
Canon Medicalの主席研究員であるKeith Goatman氏は「AIのスピードと精度は中皮腫の治療に幅広い影響を与える可能性があります。正確な腫瘍体積の測定は手作業では時間がかかり過ぎます。測定の自動化は腫瘍体積のわずかな変化も検出し、新しい治療法への臨床試験の道を拓くでしょう」と述べている。アスベスト使用は既に各国で禁止されたものの、中皮腫患者の発生では数十年という単位での時間差をみせている。英国のみならず、日本における中皮腫による死亡数も増加の一途であり、国際的に死亡者数のピークはまだ先にあるとも予測される。当該AIツールではその先を見据えた開発が進められている。
バングラデシュにおける子供の発育阻害を明らかにするAI研究
生後初期の慢性的な栄養欠乏によって、その後年齢相応の身体および認知機能の発達が得られなくなるものを「発育阻害(stunting)」と呼ぶ。1億を超える未就学児が発育阻害に曝されるが、その90%以上がアジア・アフリカの子どもたちとなる。豪キャンベラ大学などの研究チームは、バングラデシュにおける小児発育阻害のリスク因子探索に、機械学習アプローチを用いた研究を行っている。
Informatics for Health and Social Careからオンライン公開されたチームの研究論文によると、2014年のバングラデシュにおける健康調査データを利用して、5歳未満の小児における発育阻害を予測する機械学習モデルの構築、およびリスク因子の探索を行ったという。結果から、バングラデシュにおける発育阻害への高い説明力を持つリスク因子は順に、小児の年齢、家庭の経済状況、母親の学歴、妊娠期間、父親の学歴、世帯規模、初産時の母親の年齢などが明らかにされている。
著者らは「研究成果によって、バングラデシュにおける発育阻害を理解するためには、社会経済的因子に加え、栄養および環境要因の観察が重要であることを明らかにした」としており、事態改善を目指した取り組み・政策立案への示唆を本研究知見が提供する事実を強調している。
関連記事:
機械学習で自閉スペクトラム症の血中バイオマーカーを特定
糞便から食生活を予測するAI研究
発熱した乳児にその検査と治療は必要か? – 低リスク患児を特定するAIモデル
アクションゲームがADHD向けデジタル治療としてFDA認証を取得
産後うつ病を予測する機械学習アルゴリズム
産後うつ病は出産経験女性の10%が罹患し、時に患者自身または子に対して深刻な転帰をもたらす重要疾患とされている。うつ病の既往は主要なリスク因子として知られているが、明確な病因は未だ明らかにされていない。スウェーデン・インド・ドイツなどの国際共同研究チームは「産後うつ病の発症を予測する機械学習アルゴリズム」を構築した。
Scientific Reportsから12日公開されたチームの研究論文によると、スウェーデン・ウプサラにおいて2009年から2018年までの間に実施された前向きコホート研究から、ベースとなるデータが収集されたという。4,313名の臨床データ・属性データ・心理測定データなどから産後うつ病の発症を予測する機械学習アルゴリズムを導いたところ、精度73%・感度72%・特異度75%と臨床的に有用と言えるパフォーマンスを示していた。一方、出産以前にメンタルヘルスの問題が無かった女性については、予測精度が64%へと低下する事実も認めている。また、産後うつ病の発症予測に対して高い説明力を示した変数は、妊娠中のうつ病と不安、回復力、性格に関連する変数などであった。
産後うつ病は、その罹患リスクを見過ごすことができない程度に高い頻度でみられる一方、適切な診断と治療介入を受けているのは一部に過ぎない。研究チームは、予測モデルに基づく個別フォローアップと費用対効果の高い管理指針策定を目指し、アルゴリズム精度の向上と個別リスク因子の有効利用を検討している。
関連記事:
うつ病と双極性障害を鑑別する機械学習アルゴリズム
AIとメンタルヘルス – がん患者におけるうつ病リスクの自動評価
妊婦の感情と精神状態へのAI応用に発展の余地 – セビリア大学からのレビュー論文
スタンフォード大学 – 機械学習手法による妊娠高血圧腎症の早期予測
機械学習による舌がんの個別化予後予測
舌がんは口腔発生のがんで最も頻度が高く、治療の遅れが死亡者増へとつながり、治療に伴う言語障害や嚥下障害も問題となる。舌がんのリスクを適切に層別化し、再発や全生存期間など転帰を予測する機械学習ツールが、フィンランドのヴァーサ大学から発表予定である。
フィンランドのメディア Mediiuutiseteでは、同研究と著者のRasheed Alabi氏を紹介している。Alabi氏の博士論文「Machine learning for personalized prognostication of tongue cancer」は来る4月15日にヴァーサ大学で審査される予定であり、その予測モデルは治療後の舌がん再発率を88.2%の精度で予測している。舌がん患者の全生存期間の予測についても、従来の病期分類やノモグラムを上回る結果を示したという。
同研究はフィンランドの5つの教育病院、およびブラジルのA.C.Camargoがんセンター、米国立衛生研究所の患者データが用いられた。従来のTNM分類は、がん患者の予後を予測する客観的で普遍的なツールであるが、特に早期舌がんに対する予測力には限界があることが指摘されてきた。より予測精度の高いシステムによって、口腔機能に影響するような、効果の乏しい治療や過剰な治療を防ぐことが期待される。
Microsoftの医療AI進出 – Nuanceを197億ドルで買収
Microsoftは12日、Nuance Communicationsを197億ドル(約2兆1555億円)で買収することを明らかにした。買収額は全額現金で支払われ、Microsoftは医療AI事業への本格参入を実現する。
速報記事:Microsoft - 米Nuanceの買収交渉か?
Microsoftの発表によると、Nuanceの現CEOであるMark Benjamin氏はCEO続投となり、Microsoftでクラウド・AI事業を率いるScott Guthrie副社長の直属となる。Microsoftは今回の買収を、2020年に立ち上げたMicrosoft Cloud for Healthcareをさらに成長させ、業界固有のクラウド戦略を目指す重要なステップと捉えている。
NuanceのAIソリューションは音声認識によって電子カルテ記録の自動化を進めるもので、現在、米国医師の55%以上、放射線科医の75%以上によって使用され、米国病院の実に77%において採用されている。Microsoftはついに、ヘルスケア領域における比類のない資産を手に入れた。
関連記事:
米Nuanceが医療用文書作成自動化AIのSaykaraを買収
米Nuanceの医療用音声書き起こしAI – 米最大級医療グループProvidenceと提携
Ambient Clinical Intelligence – 医師を書類作業から救うAI環境開発
非接触型バイタルサイン監視という新潮流 – イスラエル「Donisi」
脈拍数・心拍数・呼吸数といったバイタルサインを、非接触型のリモートセンシング技術によってモニタリングすることが新たな潮流となってきた。イスラエルのテルアビブ拠点で非接触型モニターを開発する「Donisi Health」は、センサーシステム「Gill Pro」でFDAのDe Novo申請(市販前審査の一種)で機器承認を得た。
MobiHealthNewsでは、Donisi社のGill Proについて紹介している。Gill Proは卓上に設置した機器が、光学センサーとAIアルゴリズムの組み合わせで人の体表レベルの微動を遠隔監視し、脈拍数・心拍数・呼吸数・呼吸速度を推定することができる。Gill Proはさらに心房細動を識別する機能へ適応拡大を目指し、FDAの申請プロセスを進めているという。
COVID-19のパンデミック以降、従来の接触型センサーから、非接触型モニターへ移行する大きな流れが鮮明となっている。スマートスピーカーで心拍をモニタリングするシステム(過去記事)や無線によるリモートセンシングでの服薬管理(過去記事)など、非接触型生体監視デバイスの大きな可能性を感じさせる発表が相次いだ。Donisi社のCMOである Sagi Polani氏は「今回の機器承認は、ライフスタイルを変えずに生活を変える、という私たちの使命を果たすためのエキサイティングな一歩です」と述べた。
関連記事:
スマートスピーカーを利用した心拍モニタリングシステム
投薬自己管理のエラーを防ぐリモートセンシング技術
2021年最新「世界の有望AIスタートアップ Top 100」
米CB Insightsによる、AIスタートアップ6,000社以上を対象としてトップ100を選出する調査「AI 100」が今年も発表された(過去記事2020年版)。
同調査が最も代表的なカテゴリーに掲げる「ヘルスケア」には最多の8社が選出されている。それらスタートアップは私たちのメディアに登場したものもあり、以下順不同で紹介する。
1. 「Caption Health」AIガイド超音波診断(過去記事)
2. 「theator」手術支援AI(過去記事)
3. 「insitro」AI創薬
4. 「Overjet」歯科X線画像診断AI
5. 「Unlearn.AI」AIによるデジタルツイン構築で臨床試験支援
6. 「Olive」医療機関の業務効率化AI(過去記事)
以下2社は昨年に続き2021年も選出
7. 「Recursion Pharmaceuticals」AI創薬(過去記事)
8. 「Owkin」研究者向けAIプラットフォーム(過去記事)
医療関連はヘルスケアのカテゴリー以外にも含まれ、特に日本からはOTHER R&Dのカテゴリーに「エクサウィザーズ」が選出されている。同社は介護や医療の領域においてAIプロダクトを開発している。その他、日本からは法務・リーガルテックを手がける「LegalForce」が選出された。100社は12カ国から選出され、米国からは昨年の65社とほぼ同様、2021年は64社が選出された(英国8社、中国とイスラエルが6社、カナダ5社と続く)。米国の調査会社ゆえに同国内からの選出が偏重する側面はあるが、AIスタートアップ勢力図が米国を中心としたものとして続くことは、実感としても間違いがない。
ClearUPのFDA承認 – 微弱電流で鼻詰まりを解消する小型デバイス
米Tivic Healthが開発するClearUPは、微弱電流によって副鼻腔の痛みを軽減するハンドヘルドデバイスとして、米食品医薬品局(FDA)の承認を取得済みである。このほどClearUPは、「アレルギー・インフルエンザ・感冒に伴う鼻詰まり」に対する追加承認を取得した。
Tivic Healthの最新プレスリリースによると、ClearUPは、デバイスを頬・鼻・眉骨に沿って滑らせることで同部に微弱電流を流し、皮膚直下の神経刺激によって症状緩和を期待するもの。同社による臨床研究では、ClearUP導入後10分程度で平均35%に症状の軽減がみられ、4週間に渡る定期使用では平均44%の症状緩和が報告されたという。昨年春段階でCEマークは取得済みであり、今回のFDA承認と併せ、ClearUPの取り扱いマーケットは190カ国以上にもなるとする。
Tivic HealthでCEOを務めるJennifer Ernst氏は「我々は薬や化学薬品に頼ることのないソリューションを、無数の人々に届けられることを誇りに思う」と述べ、デバイスの質的改良を継続すること、および他の炎症性疾患に対する効果検証にも積極的に取り組む姿勢を明らかにしている。
関連記事:
スマートスピーカーを利用した心拍モニタリングシステム
SpeechVive – 耳掛け型ウェアラブルデバイスでパーキンソン病患者の発声訓練
周囲の咳の音から感染症アウトブレイクを監視 – ポータブルAIデバイス FluSense
医療AIに参入する開発者がエッジAIを学ぶべき理由
Microsoft – 米Nuanceの買収交渉か?
AIと音声認識技術で知られる米Nuance Communicationsに対し、Microsoftが買収交渉を続けているという。
12日、Bloombergが報じたところによると、この協議がまとまれば買収額は160億ドルにものぼる可能性があり、Microsoftにとっても過去最大規模の買収劇の1つとなる(最大は2016年、LinkedInの240億ドルでの買収)。
MicrosoftとNuanceは2019年以来、医師・患者間の診察時音声から電子カルテ上への自動記載と情報分類を行うシステムについて、生産的なパートナーシップを維持してきた。近年、GoogleやAmazonなどのライバル企業がヘルスケア領域への投資を加速させており、Microsoftの動向にも大きな関心が集まっている。
関連記事:
米Nuanceが医療用文書作成自動化AIのSaykaraを買収
米Nuanceの医療用音声書き起こしAI – 米最大級医療グループProvidenceと提携
Ambient Clinical Intelligence – 医師を書類作業から救うAI環境開発